
受験の国語の読解には「鉄則・作法」があります。
そのルールを守って読んでいかないと、いつまで経っても、安定して高得点を
取ることはできません。
以下、私(武蔵野拓:プロの編集者です。学術出版社に勤務していたころは、
東大、東工大、一橋大はじめ、最難関大学の教授たちに指示して本を書かせ
て来ましたwww)が、長年の経験からエッセンスを凝縮した
「受験国語の読み方・解き方」
についての話となります。
中学受験:国語の読解:こんなことで悩んでいませんか?
・国語は「なんとなく」「感覚で」読んでいる(解いている)
・本文や問題文に何も書きこまずに読んでいる
・国語の点数、偏差値が安定しない
・得意な分野はそれなりにできるけど、苦手な内容だといつも低偏差値
・小説は得意だけど、評論は苦手(またはその逆)
・どうしても四谷大塚の偏差値で50を超えない
・そもそも、問題文をきちんと読めていない
「え?うちの子のこと?」
と思った、そこのあなた。
小学生~中学生~高校生~大学生~社会人まで、症例10000以上を
みているので、
「国語ができる理由」も分かれば、「国語が安定しない理由・原因」も
分かるのです。
そこを診断して、治療をして、読み方・解き方を矯正してあげれば、
少なくとも今よりも成績が上がる事はほぼ間違いがありません。
中学受験・国語読解ルール集・3原則と10の鉄則!チェック表
| 【3原則+10の鉄則】 | ☑チェック欄 |
| 原則1 「なんとなく」禁止! | |
| 原則2 根拠(証拠)は本文中! | |
| 原則3 本文・問題文には必ず書きこむこと | |
| 【評論文】 | |
| 鉄則1 論理を追う(大枠):「●●●●●」の部分を探す! | |
| 鉄則2 本文への書き込み | |
| 鉄則3 問題(問題文)は●●●●●→何が聞かれているかを丁寧に | |
| 鉄則4 選択肢は●●で区切る+××を使う | |
| 【小説・物語文】 | |
| 鉄則5 登場人物の「●●」を追う(▲か■か) | |
| 鉄則6 ●●●●●を○で囲む | |
| 鉄則7 ●●●●●したら●●「ピ~ッ」●●●●●を引く | |
| 鉄則8 主人公(登場人物)の●●●●●に注目 | |
| 鉄則9 問題(問題文)は●●●●●→何が聞かれているかを丁寧に | |
| 鉄則10 選択肢は●●で区切る+××を使う:●●●●●全集中! |
*鉄則3と鉄則9、鉄則4と鉄則10は、基本的にはほぼ同じ内容ですが、チェックしやすいように両ジャンルに入れています
(伏字無しのチェック表のPDFファイルがあります。購入後に印刷してご利用ください)
読解の鉄則・作法を知らなければ基本的にはそのままです
「受験国語の読解の鉄則・作法」を知らずに、感覚で読んでいると、
基本的には最後までそのままです。
きちんと習わずにピアノを弾くようなイメージです。
ドレミファソラシドはできても、そこから先に進めないという感じですね。
厳しい現実を書きますが、読解力を鍛えるべき時に鍛えないと、一生「読めない」
ままです。
そして、中学受験の問題は、そういった我流の読み方をする子、
感覚・なんとなくで読んでいる子を容赦なく間違えさせるものになっています。
面白いくらいに誤答を連発します。
結果として、偏差値は上がらず、受験には落ちるという事になります…。
「国語」はそもそも【勉強方法:解き方】が分かっていない子が多いです。
そのためきちんとした解法で訓練を続けるとかなり「差」が出る科目でも
あります。「差」は偏差値に直結します。
ではどうすればいいのか?
では、そうならないためにどうすればいいのか?
【読み方、解き方の鉄則・作法を知り、それに沿って何度も練習をする】
これです。
この記事で提案している、
「中学受験・国語読解ルール集・3原則と10の鉄則!」
は、そのルール集になります。
基本的には、これについている「チェック表」を常に横に置き、
自分の(お子さんの)読み方が正しいのかどうかを気にする癖をつけます。
そして、それを繰り返す事で、自然と「チェック表」が頭に入って
きます。受験国語を読む際の焦点の当て方と考えて頂いても構いません。
一度修得すると、九九のようなもので、いちいち考えなくても
「そういう方向で読める」ようになります。そういうものだからです。
3-4年生から始める!
いつからそういった読み方をすればいいのか?
4年生くらいから始めると良いと思います。
1‐2年生の場合、まだ不要です。
もちろん、チェック表を親が手に入れて、自分の読解力を上げておく分には
全く問題ありませんが、1‐2年生に、この読み方をさせるのはおそらく
オーバースペックです。
3年生くらいからは、成長が早い子は理解できてくると思います。
ですが、4年生以降は早い方がいいです。
理由は、修得に一定の時間がかかるからです。
鉄則・作法を覚えて、受験国語の読み方を体に沁み込ませるのに、
最低半年~1年はかかります。
また、2年以上きちんとやると、ほぼできるようになります。
ですので、始めるなら、4年生以降できるだけ早くです。
6年生の12月でも遅くはないか?
正直、厳しいです。もちろん、それなりの読解力がついている子が確認のために
使うのであれば有効(もしかしたら大きな成果を発揮する)かもしれません。
具体的には四谷大塚の合不合偏差値で50以上の子です。
ただし、まったく読み方や本文や問題文への書き込みを習っていない子が、
初めてやって、1か月そこらではなかなか難しいと思います。
4年生からはやるなら早くです。
え?5年生ですか?
すぐに始めてください。すぐに。
それに、読解力は、一生ものですので、何も中学受験でしか使えないという
事はまったくありません。むしろ、大人にこそ読んでもらいたいです。
(そういった意味で言うと、中学受験には間に合わないかもしれませんが、
6年生の冬であっても意味はありますね)
購入はこちらからどうぞ
■内容説明■
・下記に実物見本があります
・「3原則と10の鉄則」PDFのチェック表(印刷してご利用ください)
・「3原則と10の鉄則」の詳細解説(会員制のブログ記事になります)
・特別メルマガへの招待(無料です)
基本的には、国語の読解の際に「チェック表」を使って、読み方・解き方が
正しいかどうかを確認し、訓練をしていく形になります。
それの繰り返しで、受験国語の正しい読み方・解き方に慣れ、精度を上げ、
正答率を上げる事を目指します。
ZOOM等を使っての私の授業と併用すると一気に効果を増します。
お値段は、2500円です。
下記LINEからご連絡頂ければスムーズです。「武蔵野さんですか?」と聞いて
頂けると混乱がなくありがたいです。

https://line.me/ti/p/2J8jtxAzmy
お問い合わせからでも構いません。ご連絡を頂ければすぐに対応いたします。
上記「問い合わせ」から何らかの不具合で送れない場合はメールでも対応可能です。
kybkhappy#gmail.com
(#を@に変えてください)
また、期間限定ではありますが、キャンペーンとして、
「中学受験・国語読解ルール集・3原則と10の鉄則!」と一回のZOOM授業(1時間)のセット
を5000円でお受けしています。
通常の授業より格安ですし、チェック表+鉄則集を自分で読むだけと、
解説を加えた授業を聞くのは全く違いますので、
もしご興味あれば、購入前に
LINE(ライン)
https://line.me/ti/p/2J8jtxAzmy
または、
ページよりご連絡をお願いします。詳細をお知らせします。
上記「問い合わせ」から何らかの不具合で送れない場合はメールでも対応可能です。
kybkhappy#gmail.com
(#を@に変えてください)
以下、
「中学受験・国語読解ルール集・3原則と10の鉄則!」
の具体的な内容見本となります。
中学受験・国語読解ルール集・3原則と10の鉄則!チェック表
| 【3原則+10の鉄則】 | ☑チェック欄 |
| 原則1 「なんとなく」禁止! | |
| 原則2 根拠(証拠)は本文中! | |
| 原則3 本文・問題文には必ず書きこむこと | |
| 【評論文】 | |
| 鉄則1 論理を追う(大枠):「●●●●●」の部分を探す! | |
| 鉄則2 本文への書き込み | |
| 鉄則3 問題(問題文)は●●●●●→何が聞かれているかを丁寧に | |
| 鉄則4 選択肢は●●で区切る+××を使う | |
| 【小説・物語文】 | |
| 鉄則5 登場人物の「●●」を追う(▲か■か) | |
| 鉄則6 ●●●●●を○で囲む | |
| 鉄則7 ●●●●●したら●●「ピ~ッ」●●●●●を引く | |
| 鉄則8 主人公(登場人物)の●●●●●に注目 | |
| 鉄則9 問題(問題文)は●●●●●→何が聞かれているかを丁寧に | |
| 鉄則10 選択肢は●●で区切る+××を使う:●●●●●全集中! |
*鉄則3と鉄則9、鉄則4と鉄則10は、基本的にはほぼ同じ内容ですが、チェックしやすいように両ジャンルに入れています
(伏字無しのチェック表のPDFファイルがあります。購入後に印刷してご利用ください)
【国語の読解:3原則と読解のルール・10の鉄則】
極端に言うと、中学受験の国語の読解で教える事は
「●●●●●」(証拠は本文)
「●●●●●」(証拠は本文)
「上記をしっかり読み解くためにどのように本文や問題に書き込んでいくか」
だけです。
「●●●●●」の方も、読み方は論理的にやるので、
究極「国語は論理」だけです。
これが本当の意味で理解できたら免許皆伝です。
これをできるようになるには、これから書いていく、
【中学受験・国語読解ルール集・鉄則!】
を傍らにおいて、何度も何度も繰り返し、
正しい読み方で練習・演習をしていく
事が必要になります。
だいたい、半年~一年(大問で100~200の物語文や評論文を解く)でそれなりに
できるようになっていきます。
「国語」はそもそも【勉強方法:解き方】が分かっていない子が多いです。
そのためきちんとした解法で訓練を続けるとかなり「差」が出る科目でも
あります。
読解の「作法」を丁寧に何度も何度も教えられないと、なかなか安定
して高得点が取れない教科です。
【国語の読解:3原則】
原則1 「なんとなく」禁止!
原則2 根拠(証拠)は本文中!
原則3 本文・問題文には必ず書きこむこと
3原則は公開しています。
中学受験・国語読解の読み方ルール集・3原則・基本編
3つの大原則・基本編は、評論(論説文)+小説(物語文)に共通した内容です。
【国語の読解:3つの大原則】
原則1 「なんとなく」禁止!
原則2 根拠(証拠)は本文中!
原則3 本文・問題文には必ず書きこむこと
原則1 「なんとなく」禁止!
評論でも小説でも、慣れないうちは、小学生は
「なんとなく」
で答えを選びがちですが、それは絶対にダメです。
「なぜこの答えか?」
という質問に答えられる形で根拠・理由をもって答えを選ぶ・書く
必要があります。
そういった意味では、国語も算数と同じです。
より具体的には下記の【原則2】をご確認ください。
原則2 根拠(証拠)は本文中!
【原則1 「なんとなく」禁止!】と書きましたが、では具体的に
どうすればいいのか?
(ここでは選択肢の問題を前提とします)
●●●●●●「根拠(証拠)」は必ず本文中から探す事です。
評論でも小説でも、選択肢を選ぶ根拠はすべて本文(から探します)にあります。
例)
「太郎は背中を丸めてトボトボ歩いていた」→●●●●●●
●●●●●●→勝てると思っていた野球の試合に負けたから
とにかく、常に「何でこの選択肢なのか?」「他の選択肢はどこが違うのか?」
を考える事が大事です。●●●●●●です。
原則3:本文・問題文には必ず書きこむこと
具体的に何を書き込むかは「応用編」で詳細に書きますが、
【本文・問題文に何も書かない読み方では安定した高得点は望めません】
そもそも、なぜ問題用紙に鉛筆で書き込みをしていく必要があるのか?
1 すぐに詳細を忘れるから
2 どこに何が書いてあるかパッと見て分かるから
です。
問題用紙に何も書かずに読んでいくのは、算数で途中式を書かないのに
似ています。必ず間違えます。
国語の読解は絶対に書き込みながら読んでいく必要があります。
文章を読んだ後に問題文を読み、「解く」という段階になったら、必ず
「もう一度問題文に戻る」
はずです。その時にはある程度は絶対に忘れています。それを前提にして、
問題用紙にポイントを書いておくことが大事です。
また、「解く」段階になると、「あれ、どこに何が書いてあったっけ?」
となる事が非常に多いです。それを防ぐためにも、必ず書きながら読む、読みながら
書くようにしましょう。
算数の、
問題文を読みながら条件整理をする
に似ています。
10の鉄則 評論(論説文):の読み方ルール集・応用編
鉄則1 論理を追う(大枠):「●●●●●」の部分を探す!
評論文・説明文は
●筆者の主張・要点があり
●それを論理的に説明している
文章です。
・筆者が立てた筋道(論理)を意識して文章を読んでいく
・国語は本文にどう書いてあるか、そもそも書いてあるかを答える科目
↓
なぜなら、国語の問題は「次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい」と必ずあるから
↓
答える根拠は本文中にある(答えは本文の中にある)
・著者が、読者(誰か分からない人)に筋道=論理を立てて説明していくのが評論文
論理=こうだからこう、こうだからこうという理屈
考え方としては、1+1=2、2×3=6の「=」とほぼ同じ。
●論理は同じ事の繰り返し●
・「イコール」の関係(筆者の主張A=具体例A’、体験談A”)
・「対立」の関係(筆者の主張と対比対立するものを並べて違いを示す)
文章の「要点」を見つける事が(論理、筋道の把握には)大事
要点=大切な部分、筆者が言いたい部分
(評論の)文章は、「要点」+「飾り(比喩や説明)」でできている
中学・高校・大学の国語入試問題は、「要点」(大切な部分、筆者が
最も言いたい部分、主張)を聞いてくる
(要点が分かったら、線を引いておく)
要点=主旨・最終結論(著者が最も伝えたい事)
「要点」を補強するために、著者は多くの「飾り」を使用する。
「要点(主張)」とイコールの関係になるものは、
「対比」「具体例」「比喩」「引用」「体験談」等々。
「要点」A、「具体例」A’、「比喩」A”といった理解をすると分かりやすい。
「A=A’」
論理の法則1:主語と述語(一文における論理関係)
一文にも要点があり、それが「主語と述語」。
主語=~~は、~~が
述語=主語とつなげて読める
例)私は今日学校へ行った。 主語「私は」、述語「行った」
論理の法則2:接続語、指示語(文と文の論理関係)
主語・述語は一文の論理構造。
文と文をつなげる論理が「接続語」。
順接の接続語:だから
逆接の接続語:しかし
イコールの接続語:すなわち、つまり、例えば
指示語:これ、それ、あれ、どれ
長い表現の繰り返しを避けるために使用
指示語が何を指すかの理解が重要((基本は「指示語の前」。後ろの場合もあり)
論理の法則3:文章全体の論理構造
●論理は同じ事の繰り返し●
・「イコール」の関係(筆者の主張A=具体例A’、体験談A”)
・「対立」の関係(筆者の主張と対比対立するものを並べて違いを示す)
「●●●●●●」の部分を探す!
評論文は、
●筆者の主張があり
●それを「例」「比較」「歴史」などで補強し
●「ほら私の言ったとおりでしょ」
という流れになるのが基本です。
ですから、多くの評論文で、
★「●●●●●●」:●●●●●●★
にあたる段落や、文章があります。
★「●●●●●●」:●●●●●●★
部分を見つけることは極めて大事です。
もちろん、そこには線+書き込みです。
「●●●●●●」「●●●●●●」「●●●●●●」
何でも良いので、書いておくことが大事です。
そこが問われるからです。
鉄則2 本文への書き込み方
では、中学受験、国語の評論文の文章中に実際に何を書き込むかですが、
1 ●●●●●●
2 ●●●●●●
これが基本です。
特に●●●●●●書いておくことは極めて大事です。
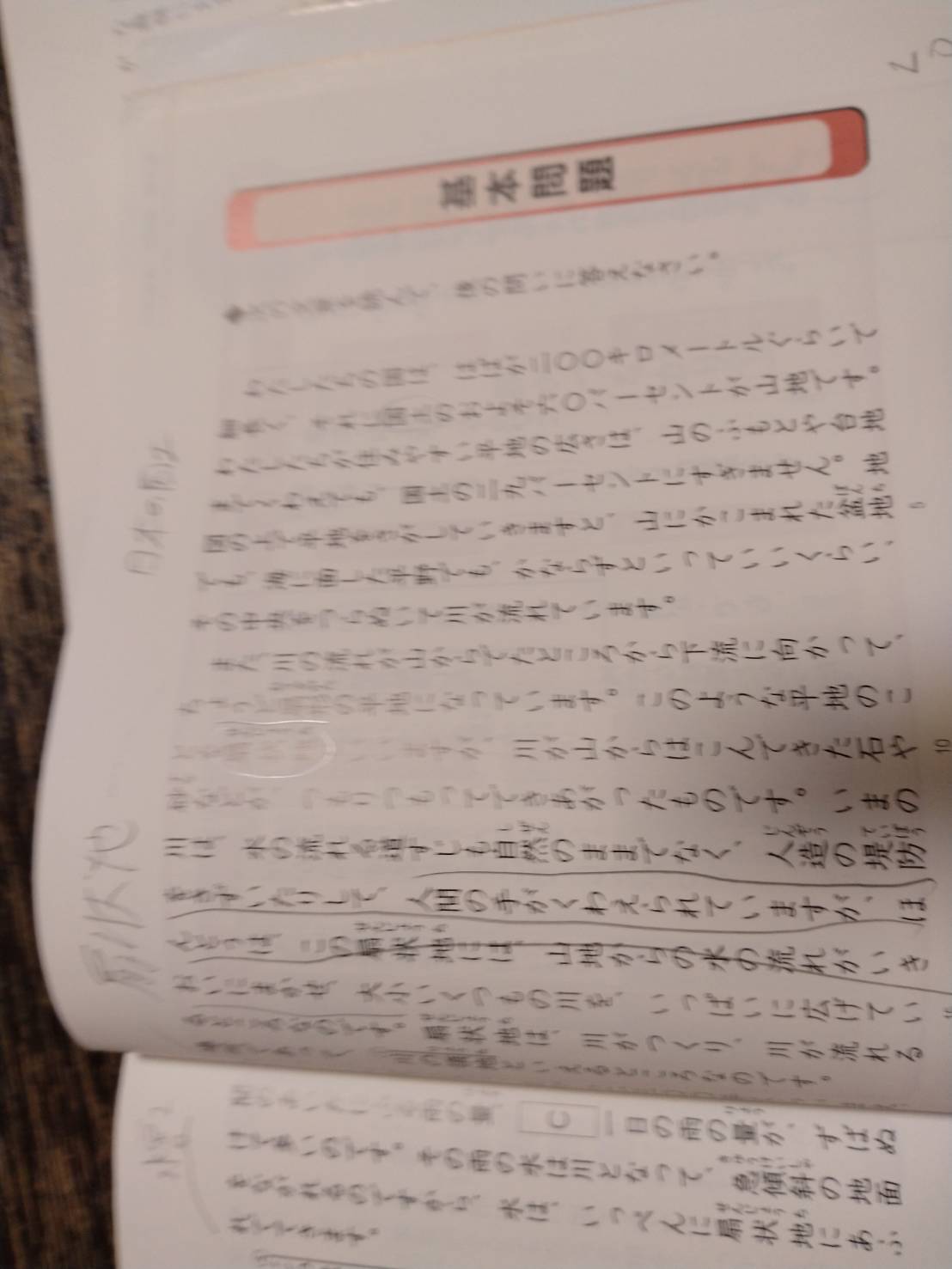
2-1 ●●●●●●にポイント・まとめを書く
具体的な書き方としては、
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
といった感じです。●●●●●●だけでもつなげると何となく
何の話か分かりそうですよね。
2-2 ●●●●●●に線を引く
評論文には、●●●●●●部分があります。
その●●●●●●と書いておくと
それだけでかなり違います。
なぜか?そこが問題として出るからです。
●●●●●●部分は、クドクドと実例を出したり、比較をしたり、いろいろと
書いてあるけど、●●●●●●のか?
と考えると良いかもしれません。
鉄則3 問題(問題文)は●●●●●●→何が聞かれているかを丁寧に
中学受験を始めたばかりの小学生の場合、大多数は、まずは
「問題をきちんと読む」=「何が聞かれているかを正確に分かる」
事がスタートです。
言い方を変えると、多くの子は、最初は
問題をきちんと読むことができず、
何が聞かれているかを正確にとらえられません。
ただし、たくさん練習する事(訓練)でその点はほとんどの場合
クリアできます。できますが、差がつく所であるのは間違いありません。
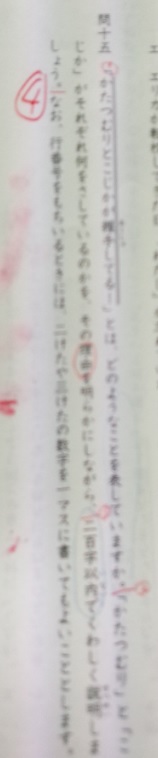
受験勉強をする際に非常に大事なマインドセット(心がけ)として、
●●●●●●答えの半分はある!
というものがあります。
言い方を変えると、
●●●●●●●を真剣に読め●
という事になります。
何故なら、「受験」「試験」というものは、基本的に
「(出された)問いに答える」
ものだからです。
出された問いに答えるという事は、まずは
●何が問われているのか?●
を正確に精緻に理解する必要があります。
極端に言えば、それ(何が問われているのかの正確な理解)が本当に
完全に100%できれば、それでその問題の半分は解けているともいえ
ます。
そういった意味では、
試験や受験は、出題者とあなた(解答者)との対話
でもあるわけです。
具体的な方法は、
▲問題文を●●●●●●●●する▲
です。
「対話」であれば、まずは相手の言った事(出された問題)をきちんと
理解し、それに対して、相手(採点者)が分かるように、問いに答える
事が大事になるのは分かりますよね?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
例)問
「かたつむりとこじかが握手してる!」とは、どのようなことを表して
いますか。「かたつむり」と「こじか」がそれぞれ何をさしているの
かを、その理由を明らかにしながら、二百字以内でくわしく説明しま
しょう。なお、行番号をもちいるときには、二けたや三けたの数字を
一マスに書いてもよいこととします。
(日能研 新小5 模試より)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲問題文を●●●●●●●●をする▲
「分かる=分ける」ですので、まずは問われている内容を
分けていきます。もちろん、問題文に書き込んでいくべきです。
(いや、書き込みなさい!)
①
「かたつむりとこじかが握手してる!」とは、どのようなことを表していますか。
②
「かたつむり」と「こじか」がそれぞれ何をさしているのかを、
その理由を明らかにしながら、二百字以内でくわしく説明しま
しょう。
③
二百字以内
④
なお、行番号をもちいるときには、二けたや三けたの数字を
一マスに書いてもよいこととします。
この4つに分けられますね?
以下のように問題文に「/」を入れて区切るのが基本です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
例)問
「かたつむりとこじかが握手してる!」とは、どのようなことを表して
いますか。/「かたつむり」と「こじか」がそれぞれ何をさしているの
かを/、その理由を明らかにしながら、/二百字以内で/くわしく説明しま
しょう。なお、行番号をもちいるときには、/二けたや三けたの数字を
一マスに書いてもよい/こととします。
(日能研 新小5 模試より)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
となると、これの一つずつに答えていき、2百字以内でまとめ
れば良いわけです。
とすると、この問題は、問題文の中に、「答えのヒント」が
かなりハッキリと書かれている事が分かりますね?
鉄則4 選択肢は●●●●●●で区切る+●●●●●●を使う:●●●●●●そこから全集中!
解答の選択肢の読み方もコツがあります。
1 選択肢は●●●●●●で区切る
国語の選択肢は、当然、長く、紛らわしくしてきます。
ですが、【●●●●●●同じ(正解)】というパターンが非常に多いです。
つまり、
【●●●●●●、その●●●●●●を吟味する】
このクセをつけるのが良いと思います。
言い方を変えると、●●●●●●を丁寧に分けるようにするという事ですね。
ボンヤリと読んでいるうちは安定して高い正答率にはなりづらいです。
2 選択肢は●●●●●●を使う:●●●●●●そこから全集中!
選択肢は、(正解が一つの場合)基本的に●●●●●●
事が多いです。
選択肢を●●●●●●たら、その●●●●●●に全集中し、証拠を本文に
探して正答を出す、というのが基本となります。
その●●●●●●をとりあえず●●●●●●にしてというイメージです。
小説(物語文):の読み方
鉄則5 登場人物の「●●●●●●」を追う(●●●か●●●か)
登場人物の●●●●を場面の中から読み取る
これが、小説・物語文の8割位を占めます。
ですので、登場人物の●●●●が出てきたらそこに線です。
登場人物の●●●●が出てきたらそこに線
登場人物の●●●●が出てきたらそこに線です。
例えば、
「●●●●」
です。
理由は?原因は?
例えば、
●●●●
「●●●●」気持の表現方法は「●●●●」
「説明」ではなく「描写」→●●●●とは書かずに、「描写」する
「突然背を向ける」 「石ころを蹴飛ばす」
●●●●の方法は大きく3つ
1 ●●●●
突然黙り込むなど。
2 ●●●●
●●●●は「発言=気持」とは限らない。
発言以外の部分に「●●●●」の根拠をきちんと見つける事が大事
3 ●●●●
「●●●●」=「気持」+「●●●●」
「●●●●」の根拠は必ず本文中から探す
「原則2 根拠(証拠)は本文中!」の事です。
「●●●●」の根拠となる、
「●●●●」「●●●●」「●●●●」
は必ず本文中にある。
「●●●●」を前後から根拠で補強して客観的に判断する。
鉄則6 ●●●●●●●●を○で囲む
これは、小説・物語文の具体的な本文への書き込み方です。
初めて読む物語文の場合、そもそも「●●●●」を忘れてしまいがちです。
そして、「●●●●」が聞かれる事が多いので、●●●●をチェックしておく
事は大事です。
ただし、●●●●の●●●●が何度も出てくる事もあるため、
●●●●に●●●●ところだけ、●●●●●●●●を○で囲います。
鉄則7 ●●●●したら●●●●「ピ~ッ」と●●●●引く
●●●●●●●●したら、そこに●●●●ピ~ッと●●●●を引いておくと、
問題を解くときに見やすくなります。
また、本文に場面が展開した事が分かる部分も多々あります。
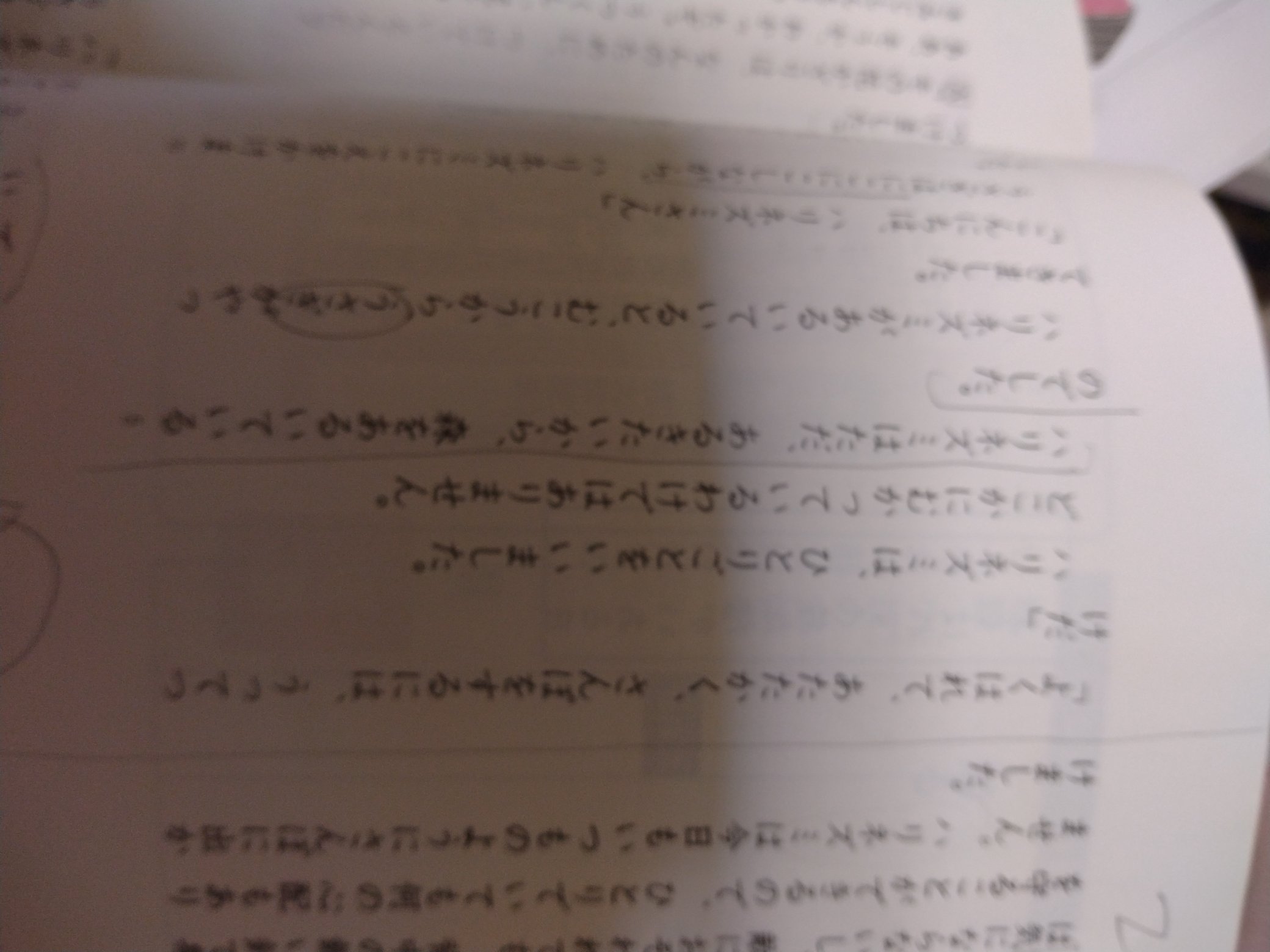
・●●●●いている
・●●●●と書いてある
・●●●●ついている
等です。上の画像の場合、●●●●いますね。その前までは、●●●●の説明で、
●●●●て、そこから散歩の●●●●●●●●ています。
回想(思い出している事)や、過去と今の転換など、とにかく、
●●●●●●●●いたら、
●●●●をピ~~ッと●●●●ください。
鉄則8 主人公(登場人物)の●●●●●●●●に注目
簡単に言うと、
・登場人物の「●●●●」
と
・主人公の「●●●●」(●●●●)
が問題になりやすい(ほぼ確実になる)という事です。
中学受験の国語の入試問題の場合、
ほとんどの物語文・小説文では、一部が抜粋されています。
その中で、主人公(仮に「花子さん」とします)が、何らかの事件や出来事に
遭遇します。
花子さんが遭遇する出来事や事件には、
・●●●●の関係
・●●●●関係(●●●●との関係)
・●●●●との関係
・●●●●とのやりとり
等があります。
まずは、それぞれの場面での、登場人物の「●●●●」に注意します。
その際に、
●●●●等々
か
●●●●
かで見る癖をつけると良いです。
「●●●●」の●●●●も大事です。
例えば、●●●●●●●●●●●●に
気づいたなどですね。●●●●から●●●●への●●●●です。
そして、多くの中学入試の国語の問題の物語文では、
(抜粋された場面の中で)登場人物・花子さんが●●●●します。
多いのは「●●●●関係」でしょうね。
例えば、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
略
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
こんな感じですね。
鉄則9 問題(問題文)は●●●●●●●●→何が聞かれているかを丁寧に
問題文の読み方、書き込み方は「評論」も「小説・物語文」も同じです。
鉄則10 選択肢は●●●●で区切る+●●●●を使う:●●●●そこから全集中!
問題文の読み方、書き込み方は「評論」も「小説・物語文」も同じです。
購入はこちらからどうぞ
■内容説明■
・伏字になっていますが、上記に実物見本があります
・「3原則と10の鉄則」PDFのチェック表(印刷してご利用ください)
・「3原則と10の鉄則」の詳細解説(会員制のブログ記事になります)
・特別メルマガへの招待(無料です)
基本的には、国語の読解の際に「チェック表」を使って読み方・解き方が正しいか
どうかを確認し、訓練をしていく形になります。
ZOOM等を使っての私の授業と併用するとより効果を増します。
お値段は、2500円です。
下記LINEからご連絡頂ければスムーズです。「武蔵野さんですか?」と聞いて
頂けると混乱がなくありがたいです。

LINE(ライン)
https://line.me/ti/p/2J8jtxAzmy
お問い合わせからでも構いませんので、ご連絡を頂ければすぐに対応いたします。
上記「問い合わせ」から何らかの不具合で送れない場合はメールでも対応可能です。
kybkhappy#gmail.com
(#を@に変えてください)
また、期間限定ではありますが、キャンペーンとして、
「中学受験・国語読解ルール集・3原則と10の鉄則!」と一回のZOOM授業(1時間)のセット
を5000円でお受けしています。
通常の授業より格安ですし、チェック表+鉄則集を自分で読むだけと、
解説を加えた授業を聞くのは全く違いますので、
もしご興味あれば、購入前に
ページよりご連絡をお願いします。詳細をお知らせします。
上記「問い合わせ」から何らかの不具合で送れない場合はメールでも対応可能です。
kybkhappy#gmail.com
(#を@に変えてください)
まとめ
以上、
中学受験・国語読解ルール集・3原則と10の鉄則!評論(論説文)+小説(物語文)の読み方・まとめ
でした。
添付のPDFファイルを印刷して、チェック表をルール集のように使いながら、
【(受験の国語として)正しい読み方ができているか?】
を常に意識しながらやるようにするだけでだいぶ違います。
【中学受験・国語読解ルール集・3原則と10の鉄則!チェック表】
| 【3原則+10の鉄則】 | ☑チェック欄 |
| 原則1 「なんとなく」禁止! | |
| 原則2 根拠(証拠)は本文中! | |
| 原則3 本文・問題文には必ず書きこむこと | |
| 【評論文】 | |
| 鉄則1 論理を追う(大枠) | |
| 鉄則2 本文への書き込み | |
| 鉄則3 問題(問題文)は●●●●→何が聞かれているかを丁寧に | |
| 鉄則4 選択肢は●●●●で区切る+△を使う | |
| 【小説・物語文】 | |
| 鉄則5 登場人物の「●●●●」を追う(●●●●か●●●●か) | |
| 鉄則6 ●●●●を〇で囲む | |
| 鉄則7 ●●●●したら●●●●に「ピ~ッ」と●●●●引く | |
| 鉄則8 主人公(登場人物)の●●●●に注目 | |
| 鉄則9 問題(問題文)は●●●●→何が聞かれているかを丁寧に | |
| 鉄則10 選択肢は●●●●で区切る+△を使う:●●●●そこから全集中! |
*鉄則3と鉄則9、鉄則4と鉄則10は、基本的にはほぼ同じ内容ですが、チェックしやすいように両ジャンルに入れています
(当然ですが、購入者には伏字なしのチェック表のPDFファイルをお渡しします)
お値段は、2500円です。
下記LINEからご連絡頂ければスムーズです。「武蔵野さんですか?」と聞いて
頂けると混乱がなくありがたいです。

お問い合わせからでも構いませんので、ご連絡を頂ければすぐに対応いたします。
上記「問い合わせ」から何らかの不具合で送れない場合はメールでも対応可能です。
kybkhappy#gmail.com
(#を@に変えてください)
また、期間限定ではありますが、キャンペーンとして、
「中学受験・国語読解ルール集・3原則と10の鉄則!」と一回のZOOM授業(1時間)のセット
を5000円でお受けしています。
通常の授業より格安ですし、チェック表+鉄則集を自分で読むだけと、
解説を加えた授業を聞くのは全く違いますので、
もしご興味あれば、購入前に
ページよりご連絡をお願いします。詳細をお知らせします。
上記「問い合わせ」から何らかの不具合で送れない場合はメールでも対応可能です。
kybkhappy#gmail.com
(#を@に変えてください)