
「つまり、国語の入試問題とは。 作者の意図を問うているのではなくて、
編集者の意図を問うている。」 あ、受験国語の極意がサラッと書かれてる…。
ワイの秘中の秘。一子相伝の極意が。
「つまり、国語の入試問題とは。
作者の意図を問うているのではなくて、
編集者の意図を問うている。」あ、受験国語の極意がサラッと書かれてる…。
ワイの秘中の秘。一子相伝の極意が。 https://t.co/Vi7JLQBrRN— 塾なしで中学受験するブログ→できました。 (@bunponcom) July 16, 2025
岸田奈美さん(エッセイスト)の、国語の読解・受験国語の読み方への視点として、
非常にためになる一連のツイート(ポスト)は下記に全てまとめてあります。
(内容としては、日本最難関の筑駒(筑波大駒場)の中学入試に出題された自身の
文章を自分で解いてみたらまったく解けなかったけど、担当編集者が解いたら、
見事に正答を連発したという話です)
「国語の問題に作者が答えられない」→俯瞰+客観ではないから
昔から、
「国語の受験問題を、書いた当人の作家・作者が解くと解けない」
という話は何度も繰り返されてきました。いわば定番のネタです。
もちろん、まったく解けないという事もないとは思いますが、
そういった傾向がありうる事は容易に想像できます。
理由は、
作家・作者は基本的には主観的で、
俯瞰(ふかん)で見ていない(書いていない)事が多いから
です。
では、誰なら解けるのか?編集者ですね。
では、誰なら解けるのか?
編集者ですね。
「国語の問題で問われるのは、編集者の視点だ。」

では、なぜ、編集者の視点だと問題が解けるのか?
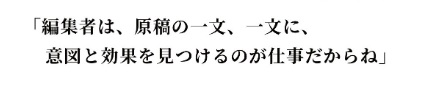
「編集者は、原稿の一文、一文に、意図と効果を見つけるのが仕事だからね」
はい、これです。
受験国語の極意・鉄則、これです。
【原稿の一文、一文に、意図と効果を見つける】
はい、これです。
編集者は、文章を読むときに、鳥の目で、上から眺めて、
「この文は、こういう効果があるな」
「ここは、意図を強めるための例だな」
「ここも、言いたい事を分かりやすくする比較だな」
といった読み方をします(しない人もいるかもしれませんが)。
編集者の視点で読むと全然違う
もうお分かりですね、
国語の問題は編集者の視点で読むと「読め方」が全然違います。
主観(自分はこう思う!)を排除し、客観的(誰にとってもそうなる)に読み、
それぞれの一文、段落が
どういった効果・意図があり、その結果
要するに何を言いたいのか
を分かりやすくしていく。
入試出題者=編集者
中学入試に限らず、入試問題の出題者は、それを逆(答え→問題→根拠→文章)
からやっているだけです。解くときは逆にすればいいのです。
文章→根拠→問題→答え(言いたい事)
(問題が最初に来ても良いですが)
もう完全に、入試出題者=編集者です。
そしたら、そっち(出題者:編集者)の視点で読めれば、それは正解を
導きやすいですよね?
まとめ
編集者の視点は一文、一文(あるいは段落)の「意図」と「効果」です。
それぞれの部分(一つ一つの文章や段落)がどういった意味や効果を
全体の中で持っているのか?その結果、
要するに何を言いたいのか。
これが分かれば、国語の入試問題なんて、安定的に高得点にならざるを得ません。
仮に、優れた読み手が高得点を取れなかったら?
それは、問題作成者(編集者)がダメ・下手なんだと、私は半ば本気で思っています。
だって、文章に込められた意図を正しく(読者や問題を解く人に)
伝えられていないのですから。
国語の入試問題とは作者の意図を問うているのではなくて、 編集者の意図を問うている。
【知らんかった】最難関校(筑波大学附属駒場中学校)の入試問題になったけど、
作者のくせに全然正解できなくて大喜びした話(1/7)
【知らんかった】最難関校(筑波大学附属駒場中学校)の入試問題になったけど、作者のくせに全然正解できなくて大喜びした話(1/7) pic.twitter.com/ysUpFviBwc
— 岸田奈美|Nami Kishida (@namikishida) July 16, 2025

























