
日本三大随筆: 『枕草子』、『方丈記』、『徒然草』についてまとめました。
歴史(文化史)としても大事です。
そもそも「随筆」とは?「小説」と比べると分かりやすいかもしれません。
| 項目 | 随筆 | 小説 |
|---|---|---|
| 内容 | 自分の体験・思ったこと | 作り出した物語 |
| 目的 | 感じたことを伝える | 読者を楽しませる・考えさせる |
| 実・虚 | 実際の思いや出来事が多い | 想像や創作が中心 |
| 例 | 『枕草子』『徒然草』 | 『源氏物語』『坊っちゃん』 |
日本三大随筆: 枕草子、方丈記、徒然草:中学受験のポイント
| タイトル | 作者 | 成立年代 | 冒頭の文 |
| 枕草子 | 清少納言 | 1000年頃(平安中期) | 春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは、すこしあかりて… |
| 方丈記 | 鴨長明 | 1212年(鎌倉時代初期) | ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。 |
| 徒然草 | 吉田兼好 | 1330年ごろ(鎌倉時代末期) | つれづれなるままに、日ぐらし硯に向かひて、心にうつりゆくよしなし事を… |
日本三大随筆: 枕草子、方丈記、徒然草の内容のポイント
『枕草子』は宮廷生活や自然の美を観察的に記した随筆。

| 季節 | 良いとされる時 | 原文(冒頭部分) | 意味(現代語風) |
|---|---|---|---|
| 春 | あけぼの(夜明け) | 春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは、すこしあかりて… | 春は夜明けがいい。だんだん空が白んで山際が明るくなり、紫がかった雲が細くたなびいているころ。 |
| 夏 | 夜 | 夏は夜。月のころはさらなり、闇もなほ、ほたるの多く飛びちがひたる… | 夏は夜がいい。月の出ている夜はもちろん、真っ暗な夜もホタルが多く飛んでいるのが美しい。雨の夜もしみじみ趣がある。 |
| 秋 | 夕暮れ | 秋は夕暮れ。夕日のさして山の端いと近うなりたるに… | 秋は夕暮れがいい。夕日が山の端に近づき、雁が列をなして飛ぶ。日が沈んでから烏が帰る姿、風にそよぐ草木なども趣深い。 |
| 冬 | つとめて(早朝) | 冬はつとめて。雪の降りたるはいふべきにもあらず… | 冬は早朝がいい。雪が降った朝は言うまでもなく、霜が降りた朝や火をおこして炭火をおこしているのもよい。 |
『方丈記』は無常観と隠遁生活をテーマにした随筆。
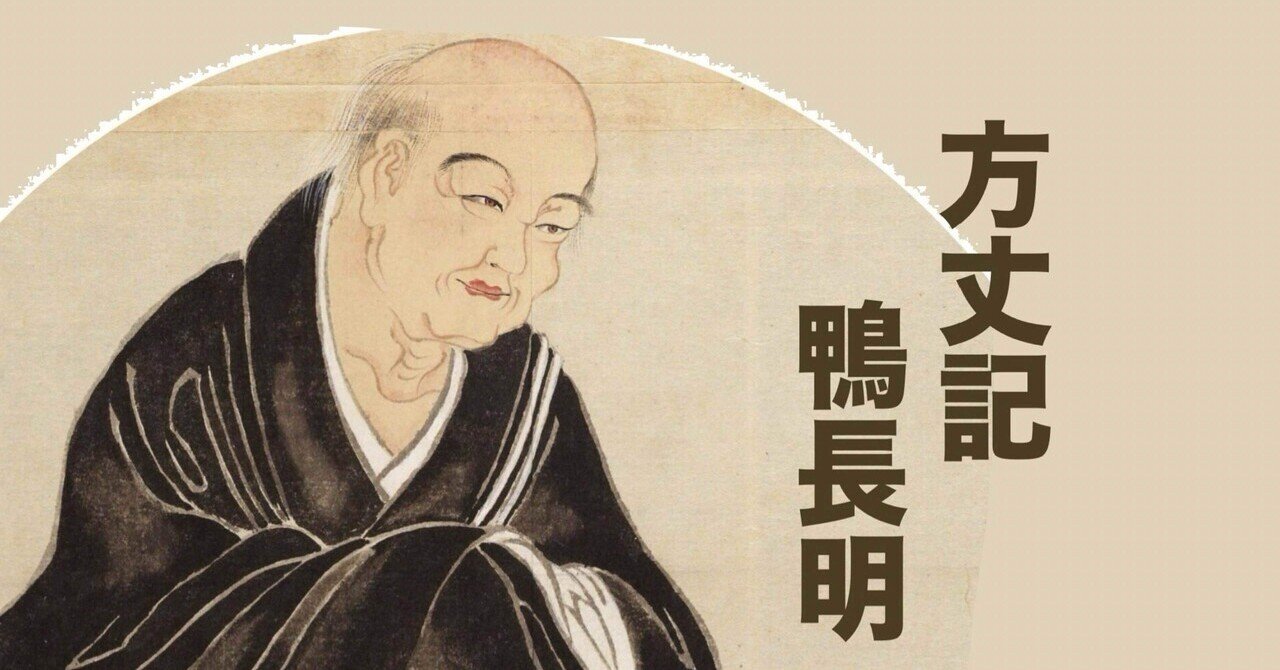
1. 無常観を示す有名な一節
「世にふるほど、人に知られぬは、いとあやしきことなり。」
(意味)
この世に長く生きていながら、世の無常を知らない人がいるのは不思議だ。
2. 方丈の庵(隠遁生活)の描写
「方丈の庵は、南に面して、東西に二間、南北に二間なり。」
(意味)
私の庵は、四畳半ほどの小さなものだ。南向きで、東西・南北ともに二間(約3.6m)にすぎない。
→ シンプルな庵の生活描写が後世の「簡素な暮らし」の象徴になっています。
3. 火事・辻風・地震など災害記録
とくに 大火の記述 は有名です。
「おびただしき火の手、たちまちに起こりて、炎天をさかのぼり、雲霞のごとくなびきて…」
(意味)
恐ろしいほどの火の手がたちまち上がり、炎は天にまで昇り、雲や霞のように広がっていった。
4. 閑居の心境
「心に静かなれば、身の貧しきことを憂えず。」
(意味)
心が静かであれば、身の貧しさなどは苦にならない。
つまり『方丈記』は、
-
冒頭の「無常観」
-
災害の生々しい記録(大火・地震・飢饉)
-
方丈の庵と隠遁生活の描写
が特に有名なポイントです。
| タイトル | 作者 | 成立年代 | 冒頭の文 |
| 枕草子 | 清少納言 | 1000年頃(平安中期) | 春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは、すこしあかりて… |
| 方丈記 | 鴨長明 | 1212年(鎌倉時代初期) | ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。 |
| 徒然草 | 吉田兼好 | 1330年ごろ(鎌倉時代末期) | つれづれなるままに、日ぐらし硯に向かひて、心にうつりゆくよしなし事を… |
『徒然草』は多彩な人生論・世評を含む随筆。
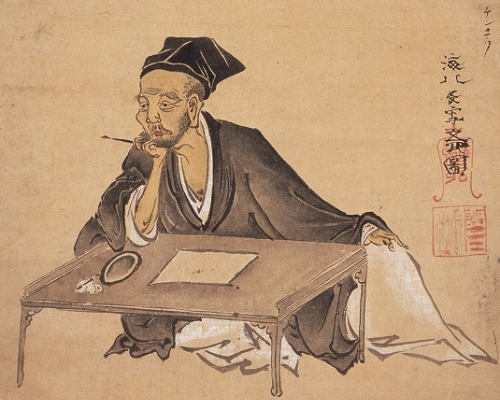
花は盛りに、月はくまなきをのみ見るものかは。
(意味)
花は満開のとき、月は曇りのないときだけが美しいというのではない。
→ 不完全さにも趣がある、という「をかし」の美意識を示す一節。
高名の木登りといひしをのこ、人に木のぼりを教ふるに…
(意味)
「名高い木登りの名人」が弟子に登り方を教えるとき、必ず「降り方」を厳しく指導した。登るよりも降りるときこそ危険だからである。
→ 人生訓・教訓としてよく引用される話。
命あるものを見るに、人ばかり久しきはなし。
(意味)
生き物の中で、人間ほど長生きするものはない。
→ だからこそ「その長い生をどう生きるか」が問われる、という人生観の一節。
まとめ―日本三大随筆: 枕草子、方丈記、徒然草:中学受験のポイント
| タイトル | 作者 | 成立年代 | 冒頭の文 |
| 枕草子 | 清少納言 | 1000年頃(平安中期) | 春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは、すこしあかりて… |
| 方丈記 | 鴨長明 | 1212年(鎌倉時代初期) | ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。 |
| 徒然草 | 吉田兼好 | 1330年ごろ(鎌倉時代末期) | つれづれなるままに、日ぐらし硯に向かひて、心にうつりゆくよしなし事を… |