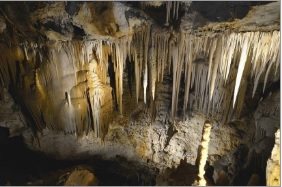
(関連記事)
地層②:隆起と沈降・しゅう曲と不整合・断層はどこまで切っているかがポイント!
地層のでき方
(山など)川の上流から、海の河口に水が流れますね?
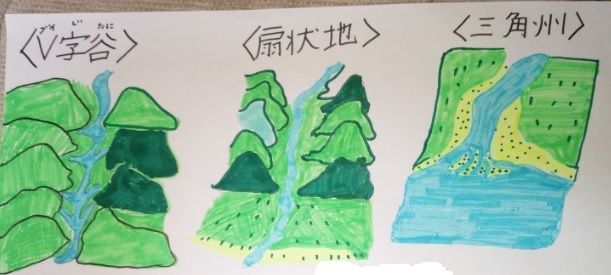
その、「川の運ぱん」で運ばれた【小石(れき)や砂、どろ(粘土)】などが
河口から海に流れこみ、海底にたい積します。
その結果、下の方から固まっていき、地層ができます。
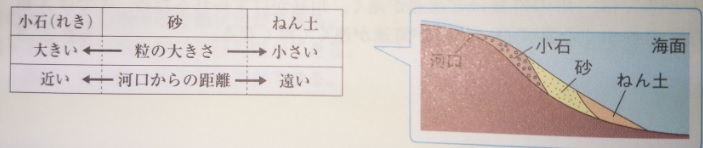
画像出典『塾技100理科』p200
上記の図の通り、陸に近い地層ほど、大きい粒の小石などで、海底深くなれば
なるほど粒の小さい粘土などになります。
【小石(れき)→砂→どろ(粘土)】
長い時間のうちに、海底だったところが陸になると、はっきりと地層が
見えるようになります。あるいは、山が削られた所や崖などで見れます。
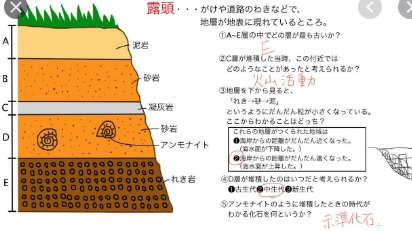


●(大地の変動がない限り)地層は下が古い(=上ほど新しい)
●(下の方の)どろ(粘土)の層は水を通しにくいので水がしみ出す事がある
たい積岩の種類
たい積岩:地層を作る押し固められた岩石
「①粒の大きさ②たい積物の成分」で分類される
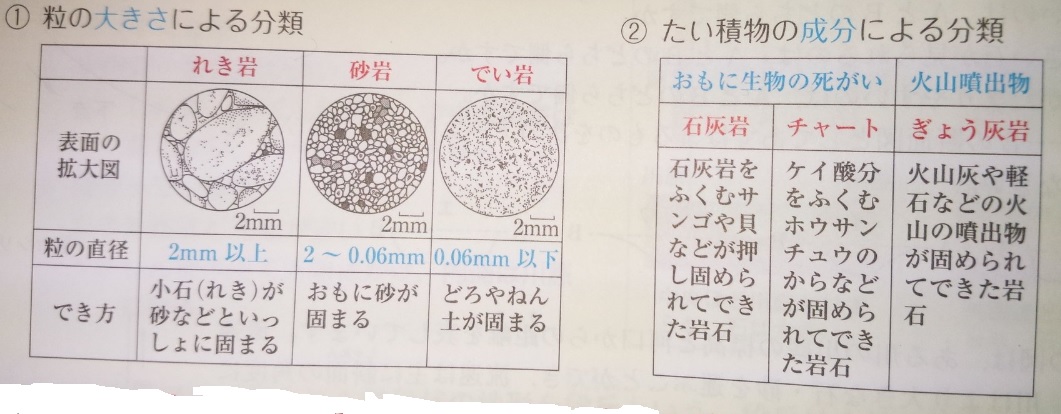
画像出典『塾技100理科』p200
point!
■たい積岩の粒は、凝灰岩(ぎょうかいがん)を除いて丸っぽい
■石灰岩に塩酸をかけると、とけて二酸化炭素が発生する
石灰岩(主な成分は炭酸カルシウム)でできた山が二酸化炭素を含む雨水で
溶か(侵食)されてできた洞窟が鍾乳洞(しょうにゅうどう)。
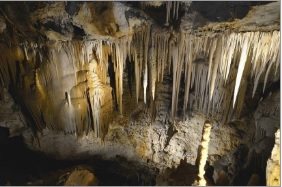
化石
【化石=地層や岩石の中に生物の死がい等の生活の跡が残されたもの】
(化石は必ずしも生き物とは限らない)

示相化石(しそうかせき)と示準化石(しじゅんかせき)
示相化石:(地層がたい積した)当時の環境が分かる化石
示準化石:(地層がたい積した)年代の基準となる化石
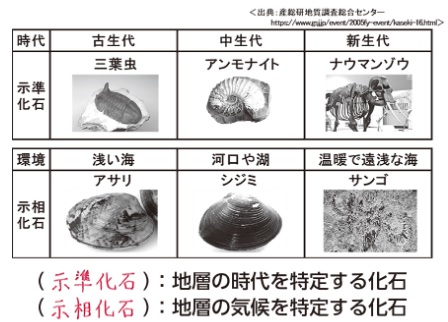
示相化石
・サンゴ:(暖かくて)浅い海 ・シジミ:河口や湖
・アサリ、ハマグリ:浅い海 ・ホタテガイ:冷たい海
示準化石
・サンヨウチュウ(三葉虫)やフズリナ→古生代
・アンモナイトや恐竜→中生代
・ナウマンゾウやマンモス→新生代
(関連記事)
地層②:隆起と沈降・しゅう曲と不整合・断層はどこまで切っているかがポイント!