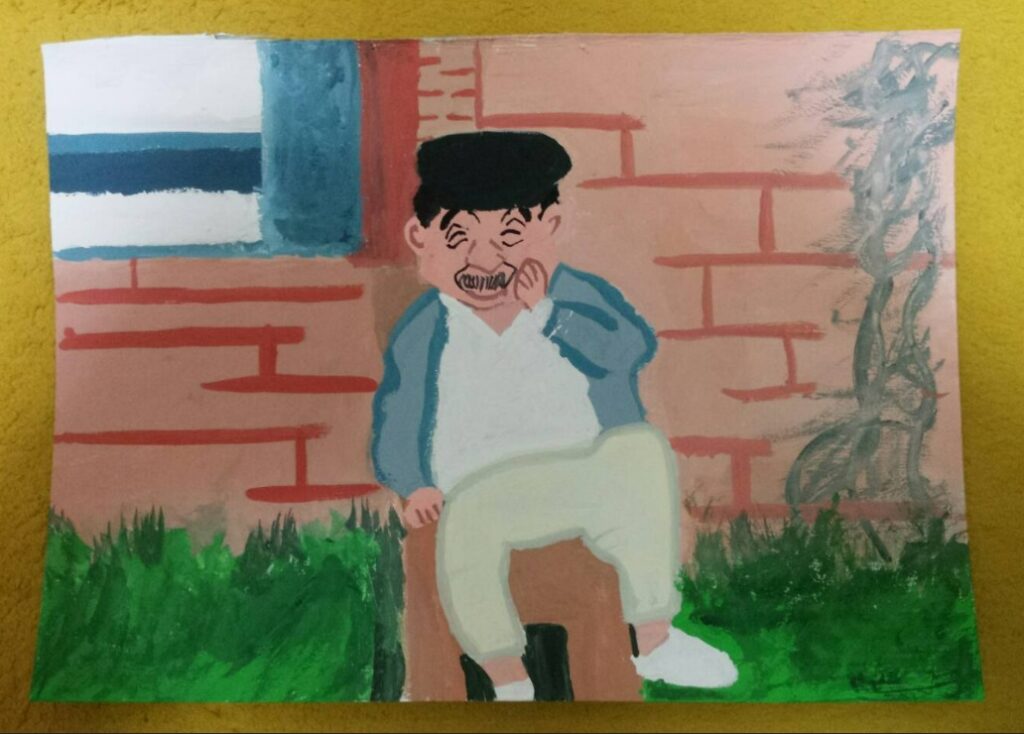
中学受験の塾の宿題が終わらずに小3~小4の子供の寝る時間が23時を
まわってしまう事が頻繁にあったりしませんか?
あるいは、子供が塾の宿題が終わらずに泣きだしそうになりながら
やったりしていませんか?
この辺りの事は、「中学受験のあるある」です。
この記事では、
「中学受験で塾の宿題が終わらない場合の対処法!」
として、「多すぎる塾の宿題」との付き合い方を含めまとめています。
「中学受験・塾・宿題・終わらない」
といった事で困っている方は是非参考にしてください。
先に結論:中学受験で塾の宿題が終わらない場合の5つの対処法!
【中学受験で塾の宿題が終わらない場合の5つの対処法!】
1 優先順位の再確認:塾の宿題は最優先ではない
2 問題の所在を確認:基礎学力?机に向かう習慣?絶対量?
3 方針を決める:家族で「どこまでやるか」を確認
4 何年生かで対応・対処法も変わる
5 1~4を総合的に親が判断する
中学受験の塾にとって「宿題」とは何か?
まず「敵」を知らなければなりません(笑)。
敵ではないにしても、「塾の宿題」というものをきちんと理解しましょう。
SAPIX、四谷大塚、日能研、ena、早稲田アカデミー等々、中学受験の
塾は多々あります。まず確認すべきは、すべてが「営利企業」だという
事です。
ですから、「塾」には塾の都合があって「宿題」を大量に出しています。
どういった都合でしょう?
中学受験の塾にとって「宿題」とは、
1 授業時間だけでは足りない部分を補うもの
2 必要な演習や定着のための復習
3 生徒の振るい落とし(残った子を「上のクラス」で鍛える)
です。
中受の塾といっても、週に2回~4回程度が一般的です。
(6年生の追い込みで「サンデーなんとか」等々で週6日!とかもありますが…)
中学受験の範囲をその時間内だけで丁寧に説明・解説するのは
物理的に難しいです。
そのために、「家でやらせる(宿題)」必要が絶対的にあります。
1 授業時間だけでは足りない部分を補うもの
2 必要な演習や定着のための復習
ですね。
特にサピックスのように「復習主義」を取り入れているような
所は、当然、復習のための宿題がたくさん出されます。
もちろん、四谷大塚だろうが日能研だろうが、宿題が多いのは
どこも同じです。
さらに、これは塾側は言わないでしょうが、「大量の宿題」は、
3 生徒の振るい落とし(残った子を「上のクラス」で鍛える)
のために使っているというのが一般的でしょう。
後ほど解説しますが、大量の塾の宿題をこなせない子は、まだ基本が
できていない子が多いです。
塾側としては、その後、進学実績に貢献してくれそうな「上のクラスの子」
と「いわゆるお客様」となるそれ以外のクラスの子をある程度早めに分けて
しまいたいというのが実際の所だと思われます。
中学受験で塾の宿題が終わらない場合の5つの対処法!
【中学受験で塾の宿題が終わらない場合の5つの対処法!】
1 優先順位の再確認:塾の宿題は最優先ではない
2 問題の所在を確認:基礎学力?机に向かう習慣?絶対量?
3 方針を決める:家族で「どこまでやるか」を確認
4 何年生かで対応・対処法も変わる
5 1~4を総合的に親が判断する
一つ一つみていきます。
1 優先順位の再確認:塾の宿題は最優先ではない
塾の宿題=中学受験ではありません。
仮に優先順位を「1志望校の合格」に置くにしても、塾の宿題を
終わらせる事に必死になるあまり、肉体的・精神的に疲弊して
しまっては元も子もありません。
そもそも、優先順位の1位は、「子供の健康や健やかな成長」と
いう方の方が多いでしょう。
特に1年生~4年生くらいまでは、「塾の宿題が終わらない」問題を
「終わらせなければ」と過度に思う必要はないかと思います。
2 問題の所在を確認:基礎学力?机に向かう習慣?絶対量?難易度?
とはいえ、塾の宿題をやらなくて良いというわけではなく、むしろ、
やらないとついていけませんので、「なぜできないのか」という問題の
所在を確認しましょう。そちらの方が大事です。
「塾の宿題が終わらない」
というパターンで最も多いのは、
時間がかかり過ぎる=解くスピードが遅い
というものです。
解くスピードが遅いという事は、【基本が完ぺきではない】
という事です。
例えば、計算問題をやる際に、九九が即答できる子と、考え考え、
一つ一つの段を数えながらやる子ではスピードに雲泥の差が出ます。
ですから、どれだけ各教科の基本ができているかは、塾の宿題が終わらない
問題の重要なポイントです。
あまりにも時間がかかるパターンの場合、その段階では、その宿題やクラスが、
その子にはオーバーワークになっている可能性があります。
もう一つは、
小学校の2年生~4年生くらいですと、まだ、
机に向かう習慣・集中力が養われていない
事が多々あります。
そうすると、疲れて塾から帰ってきて、「塾の宿題を終わらせる」
というのはなかなかにハードです。
塾の宿題の難易度が高すぎて終わらないというパターンも多いです。
勉強の鉄則として、「徐々にハードルを上げる」というものがあります。
が、ハードルが高すぎてはだめですし、ハードルの越え方を教えてもらえ
なければそもそも越えられません。
仮に、塾の宿題の難易度が高すぎて止まってしまっているのであれば、
塾のクラスが自分の学力よりも上という可能性もあります。
もしくは、塾で習った分野を十分に習得できていない状況かもしれません。
その辺りは、やはり親が確認をしてあげる必要があります。
最後は塾の宿題の絶対量です。
中学受験の塾は、そもそもが、多めの宿題を出すのに、あえて、さらに大量の
課題を与えて小学生・塾生を振るい落とすという事はよくあります。
既に基本ができている子、勉強のセンスが良い子、根性のある子を選出
しているというイメージで良いかと思います。
自分の子供が「塾の宿題が終わらない」問題を抱えているのだとしたら、
どこが原因かをきちんと確認する必要があります。
3 方針を決める:家族で「どこまでやるか」を確認
塾というのは、お子さんを守ってくれるわけではありません。
中学受験の際の武器を与えてくれるところかもしれませんが、
自分のお子さんは自分で守るしかありません。
僕の知る限りでは、オーバーワークが過ぎると、小学生には
かなりのストレスになり、過食や精神的不安定、攻撃的な性格
などにつながる子もいるようです。
ですので、例えば、塾の宿題をこなすために、小学校低学年・中学年が
夜の11時過ぎまで起きている(やらされている)といった事が続く場合、
家族間で方針を決めるべきだと思います。
「どこまで塾の宿題をやるのか」
です。あるいは、既に書いた「問題の所在を確認」して、今の段階では
ここまでにして、いつまでにこれくらいできるように基礎を鍛えよう
など、細かなペースメークがあった方が良さそうです。
【中学受験で塾の宿題が終わらない場合の5つの対処法!】
1 優先順位の再確認:塾の宿題は最優先ではない
2 問題の所在を確認:基礎学力?机に向かう習慣?絶対量?難易度?
3 方針を決める:家族で「どこまでやるか」を確認
4 何年生かで対応・対処法も変わる
5 1~4を総合的に親が判断する
4 何年生かで対応・対処法も変わる
ここまで、「塾の宿題が終わらない」問題について考えてきましたが、
対応・対処法は何年生かで変わります。
塾の宿題が終わらない場合は子供の年齢と状況に応じて対応
するべきです。
・低学年(1~2年生)の場合はムリにやらない方が良い
・中学年(3~4年生)の場合、本人の状況を見る
・高学年(5~6年生)の場合、中学受験をするなら「やる」一択
そもそも、低学年(1-2年生)の小学生を中学受験用の進学塾に
行かせるのは個人的にはあまりおススメしません。
ですが、実際に通わせている方も多いので、書いておきます。
低学年(1-2年生)の小学生の場合、机に向かう習慣も、勉強の基本も
まだまだできていない子がほとんどですので、もし仮に、
「塾の宿題が終わらない」
問題が発生した場合は、机に向かう習慣や、勉強の基本ができるように
なるのを優先して、すぐにムリにやらせるのはやめた方がいいかも
しれません。
それよりは、
基本を完ぺきにする
事の方がこの時期は大事です。
特に、泣きながら無理やり宿題を終わらせようとしているような状況
であれば、それはやめた方が良いかもしれません(その状況で塾の宿題を
やることに特にメリットも効果もないと思います)。
中学年(3~4年生)の場合、本人の状況を見るのが良いです。
上記した、「原因」を精査して、
【基本が完ぺきではない】
のか、
【机に向かう習慣・集中力が養われていない】
のか等々です。
ただし、小学校3-4年生はまだギリギリ最後の幼児という年齢
ですので、原因を確認せずに、宿題なんだから終わるまでやれ!
的に無理やりやらせのは全く効果がないと思います。
知っている例としては、小学校3年生に中学受験塾の大量の宿題を
終わるまでやらせていたら、就寝時間が23時、24時と遅くなり、
時には25時近くなることもあったそうです。
その結果は…、本人がまるでやる気を失い、ストレスから過食となり、
高学年には中学受験どころではなくなったようです。
小学校3年生~4年生くらいですと、
塾の宿題が終わらない際に原因を確認しないで無理やりやらせるのは
かえって逆効果になると考えた方が良いでしょう。
それよりは、この時期はまだ、
基本を完ぺきにする
事の方が大事です。
過去1000人以上を教えて、良い結果が出た人たちに共通して納得・称賛してもらえたワイ語録。「受験の3カ条!1:基本が大事2:基本が大事3:1,2のルールを忘れない」
— 塾なしで中学受験するブログ→できました。 (@bunponcom) January 23, 2023
高学年(5~6年生)の場合、中学受験をするなら「やる」一択です。
小学校5年生(10歳-11歳)くらいになると、徐々に集中力も勉強の
基本もできてきます。
さらに、中学受験を本気でやるのであれば、勉強量も一気に増やす
必要があります。
ですので、高学年になって、「塾の宿題が終わらない」というのは、
中学受験を本当にするのであれば少々まずい状況です。
(もちろん、補習塾などに通っていて、中受をするわけではないといった
場合は別です)
5 1~4を総合的に親が判断する
【中学受験で塾の宿題が終わらない場合の5つの対処法!】
1 優先順位の再確認:塾の宿題は最優先ではない
2 問題の所在を確認:基礎学力?机に向かう習慣?絶対量?
3 方針を決める:家族で「どこまでやるか」を確認
4 何年生かで対応・対処法も変わる
5 1~4を総合的に親が判断する
既に書きましたが、塾は営利企業(上場している所もあります)なので、
基本的にポジショントークをしてきます。
オーバーワークで塾に自分のお子さんを潰されないためには、やはり、
小学生の場合、保護者・親が子供のやっている事を確認し、仮に、
「塾の宿題が終わらない」
という問題が起きている場合は、上記の1-4を判断して対処してあげる
べきでしょう。
既に書いたようにパターンは色々あるので、一概に正解はないわけですが、
「塾の宿題が終わらない」という問題が起きている場合、
例えば、
・塾に相談する
・転塾する
・宿題を全部はやらない
・早くできるようにする工夫をする
etc.
色々な対処法があります。
どれをどのように選ぶかは、親・保護者と小学生のお子さん自身です。
それぞれのご家庭にとっての正解を導き出せるようにする事が大事です。
まとめ:中学受験で塾の宿題が終わらない場合の5つの対処法!
【中学受験で塾の宿題が終わらない場合の5つの対処法!】
1 優先順位の再確認:塾の宿題は最優先ではない
2 問題の所在を確認:基礎学力?机に向かう習慣?絶対量?
3 方針を決める:家族で「どこまでやるか」を確認
4 何年生かで対応・対処法も変わる
5 1~4を総合的に親が判断する
中学受験において、塾との付き合い方は大事です。
ですので、「塾の大量の宿題」「塾の宿題が終わらない」という
毎年毎年発生する問題に対してどう対応していくか、対処法を
考えておくことは重要となります。
この記事がその参考になれば何よりです。
チャオ アミーゴ
(関連記事)
中学受験の塾の費用・お金・いくらかかる?SAPIX!ena!本当の金額!
進学塾・進学校でやっている勉強法はこれ!●●こそが最強の受験指導方法!

