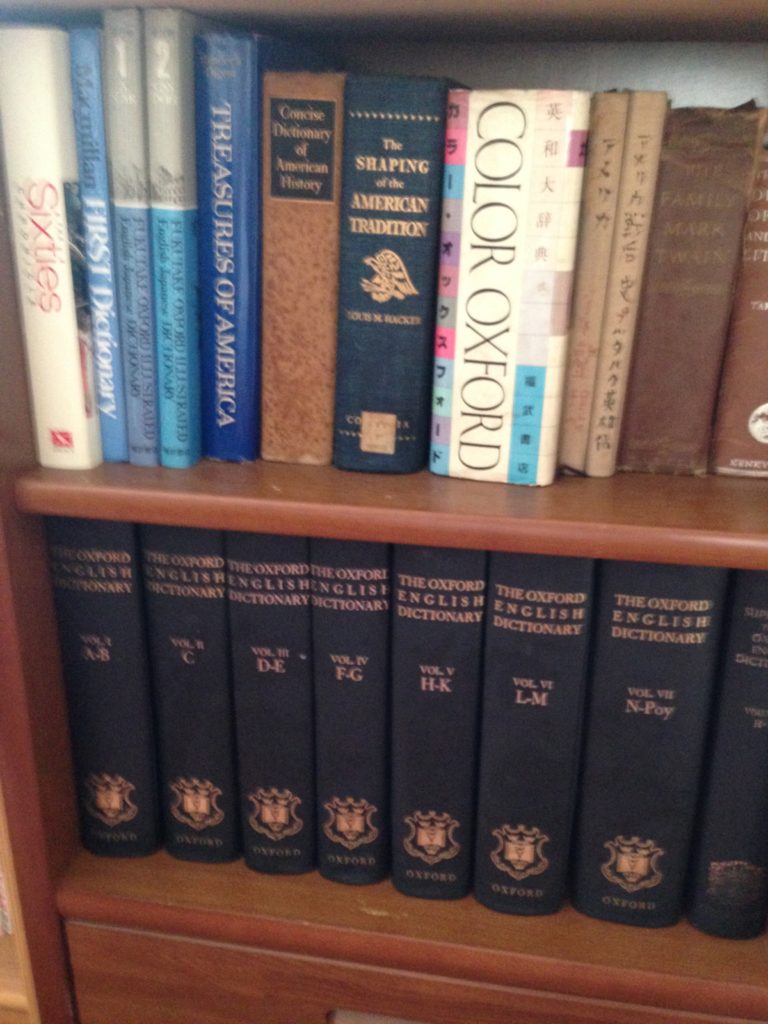
中学受験の国語:読める→解ける→速く読める→速く解けるの流れは?:中受国語の勉強法
1 読める
1-1 最初は「読めない」:作法を知らないから
1-2 作法にのっとって練習
1-3 「読める」ようになる
2 解ける
2-1 「読める」と「解ける」は別
2-2 「解く」のも作法
2-3 作法にのっとって練習
2-4 「解ける」ようになる
3 速く読める
3-1 基本は「練習」
3-2 「語い」よ「語い」:社会と理科の知識
3-3 速く読める
4 速く解ける
4-1 1-3の積み重ねが4
4-2 速く解ける=免許皆伝
一つずつ解説します。
1 読める
1-1 最初は「読めない」:作法を知らないから
国語の中学受験の勉強は最初はほとんどの子が「読めません」。
理由は「読解の作法」を知らないからです。
言い方を変えると
「論理的な読み方」:評論文・論説文
「心情を追う」:小説・物語文
等ができないからです。
試しに、まだ何も読解の勉強をしていない、3年生なら3年生、4年生なら4年生に
『予習シリーズ』(四谷大塚が出しているテキスト。早稲アカなどの大手進学塾も
使用しています)を解かせてみてください。
おそらく、まったく「読めない」はずです。
最初は以下のようになるはずです。
1 国語は「なんとなく」「感覚で」読んでいる(解いている)
2 本文や問題文に何も書きこまずに読んでいる
3 小説は得意だけど、評論は苦手(またはその逆)
4 そもそも、問題文をきちんと読めていない
(関連記事)
1-2 作法にのっとって練習
最初はほぼ誰も「読めない」ですが、これを作法にのっとって
練習していくと、結構なスピードで読めるようになってきます。
ポイントは「作法にのっとって」です。
ここでいう「作法」は、原則にのっとった論理的な読解の事です。

*上記の「チェック表」については下記の記事を参照してください
(関連記事)
「中学受験・国語読解ルール集・3原則と10の鉄則!」について
1-3 「読める」ようになる
作法にのっとった練習(それができる教師との演習が必須です)を
【10-15回位×小学校4年生以上】
続けると、だんだんと「読める」ようになってきます。
厳しい現実を書くと、
「ただ読んでいるだけ」だと、いつまで経っても変わりません。
むしろ、内容はだんだん難しくなって来るので、
5-6年生になると、相対的にできなくなってくることもよくあります
(相対的にできない=偏差値が下がるという事です)。
集団塾で、1年以上いて、上達が見られないケースのほとんどはこのパターンです。
チェック項目としては、
「本文、問題文に書き込みをしているか」
「その選択肢を選んだ理由を説明できるか」
の二点です。両方が×なら、その塾の国語の授業は
「ただ読んで、丸をつけているだけ」
です。けっこうたくさんありますよ。
2 解ける
2-1 「読める」と「解ける」は別
「1」で「読める」について説明しましたが、それと「解ける」は別です。
「解く」方も読むのと同じでルール、作法があります。

*上記の「チェック表」については下記の記事を参照してください
(関連記事)
「中学受験・国語読解ルール集・3原則と10の鉄則!」について
「解ける」という事は、
問題文を読めるようになる
と言い換える事もできます。
中学受験を始めれば、ほぼすべての伴走者(母親、父親)が経験しますが、
最初は子供たちは、問題が読めません。
「字は読めるわ!」
ですか?御冗談を。小学生のほとんどの子は、最初は本当に問題を読めません。
最初はです。「最初は」。
ほとんどの子は、聞かれている事を正確に読み取ることができない所から
スタートします。
そして、サピックスや四谷大塚に限らず、中学受験は、問題文が長い
(事が多い)です。なおさら、訓練をしていないとできません。
世知辛い世の中です。
2-2 「解く」のも作法
「読む」のと同じで「解く」のも作法です。
習わないとできません。
「問題文を区切る」
「一つずつ整理する」
「選択肢の場合、○○の表現は不正解の事が多い」
「選択肢の場合「、」の前後を分けて丁寧に読む」
「そもそも、本文に書いていない事は×」
「でも言い換えはOK。それを積極的に探す」
etc.
作法(引っかかるポイント)自体は昔から同じですが、それを何度も何度も、
やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は伸びず
です。
冗談ではなく、同じことを100回でも1000回でも言う事が大事です。
それで、国語の問題を「解く」にあたってのマナー、作法を身につけるのです。
一朝一夕でマナー(教養)は身につかないのです。
2-3 作法にのっとって練習
中学受験の国語を読んで解くにあたっての作法を身につけてきたら、
それに則って練習・練習・練習です。
「何回くらい?」
「2万回」
「2万で足りるのか?」

バスケの場合は、何度もシュート練習できるのでこれくらいの回数で良いですが、
「中学受験・国語・読解」であれば、集中した演習(優れた教師必須)で10回で
徐々に分かりだし、30回でボチボチ読めだします。
週2回×1年で100回強となりますが、それくらいやるとかなり変わります。
これまでの経験では、1年×100回ほどやった子は、5年生の一年間で、偏差値が
20以上伸び(それ以上はないというレベル)、サピ偏差値で65以上、Yで70以上が
基本になりました。一度身についた読解力は基本的に生涯落ちませんから、その後
にも役立つ事でしょう。
2-4 「解ける」ようになる
で、基本的には「読める」ようにも「解ける」ようにも
なります。
なりますが、それでゴールかと言うと、そうは問屋が卸さない。
世知辛い世の中です。
受験の場合、「速く」読めないといけません。
制限時間がありますからね。
3 速く読める
3-1 基本は「練習」
「読め」て「解け」れば、後は練習で速くできるようにはなっていきます。
ただし、一つだけ大事なポイントがあります。
「語い」(知っている言葉)です。
3-2 「語い」よ「語い」:社会と理科の知識
6年生くらいになると、国語の読解の内容もそれなりに難しいものに
なってきます。
そうすると、基本知識としての語い力がないと、スムーズに読み進める
事ができません。内容をつかみながらとなるとなおさらです。
特に社会(歴史)や理科の知識が大事です。
中学受験の国語で出題される文章にはある程度の共通点があります。
それこそ、小学生に読ませられないような内容のものは出てきません。
そうすると、ある程度方向性(パターン)は決まってきます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・現代社会の問題点(近代批判)もの:開発批判や地球温暖化問題など
・自然科学もの:動物や植物もの
・小説であれば、家族、友人関係、歴史もの
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上記のようなパターンの中に、理科や社会で学ぶ知識がかなり入ってきます。
それこそ、社会の歴史や理科の地学、生物をきちんとやっている子には、
その辺りの語い力がありますが、それがない子は、速く正確に読むことは
かなり難しいです。
ただ話せるのと、何を話せるかは全く違う概念。日本語も英語も、基礎は「語い力」なのよ「語い力」。
「8歳の帰国生はネイティブレベルの英語力があるとしても、その話す力や読み書きの力は8歳のものでしかありません」KA(帰国子女アカデミー) チャールズ・カヌーセンさんの著書『帰国子女』p15 https://t.co/dbXyjvIh1G
— 塾なしで中学受験するブログ→できました。 (@bunponcom) July 16, 2025
3-3 速く読める
「読め」て「解け」れば、後は練習で速くできるようにはなっていきます。
そこに「語い」(かなり大事)力が加わると、きちんと速く読めるように
なります。
が、簡単ではないですよ、
4 速く解ける
4-1 1-3の積み重ねが4
目次通りです。
1-3(読める・解ける・速く読める)の積み重ねが4です。
週1~2で1年以上(理想は2年以上)継続する事が大事です。
4-2 速く解ける=免許皆伝
本当に上記が全部できればはれて免許皆伝です。
中学受験の国語の問題であれば、(知ってる知らないの知識系をのぞけば)
ほぼ全問正解というのが基本になります。
おめでとうございます。
ただ、これまでに小学生~高校生、大学生、大学院生、社会人と
1000人以上に国語や英語の「読解」を教えてきたと思いますが、
免許皆伝はいません。
自分がそもそも免許皆伝ではなく、AIのように絶えず進化し続けたい
と思っていますから。
チャオ アミーゴ