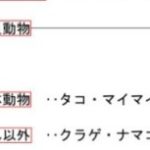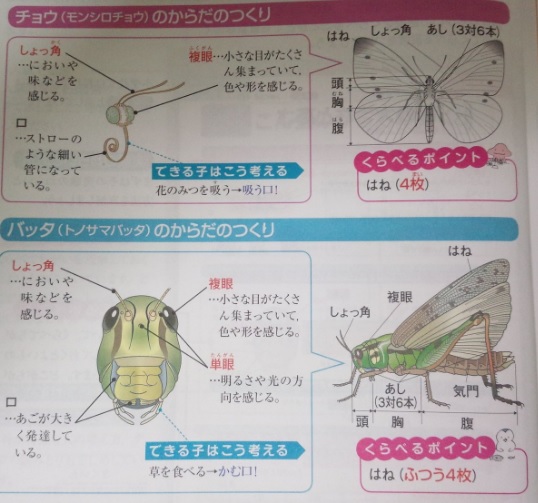
この記事のyoutube音声動画です。聴きながら読むと良いかと思われます。
「昆虫」を生物学的に正確な用語でいうと「節足動物門汎甲殻類六脚亜門昆虫綱」
というそうです・・・。今日は低気圧のようで頭が痛くなってきました(二葉亭四迷風)
ので・・・このあたりで。
●節足動物:体に節があり、節に足が生えてる
●甲殻類:体の外に硬い殻がある
●六脚亜門:足が6本(3対)ある
まとめると、
「昆虫とは、体に節があり、節に足が6本あり(3対)、体が硬い殻で覆われていている生き物」
ですね。
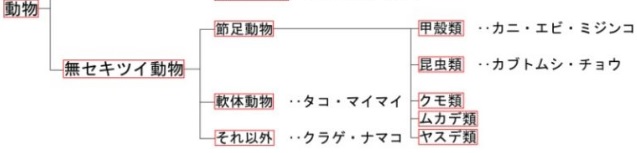
「昆虫」について勉強する場合、以下の順番でやりましょう。
1 「昆虫」の基本(体が3つとか足が6本とか):「昆虫」って何?
2 どんな種類の「昆虫」がいるか(完全変態、不完全変態とか)
3 「昆虫」ではない虫を知る(クモ類、甲殻類のダンゴムシとか)
4 「昆虫」の食べ物・棲む場所(幼虫と成虫で「変わる」のがポイント
5 「昆虫」の「冬越し」(越冬の仕方の違い)
6 色々な昆虫の卵・幼虫・成虫の姿
まずは「1~3」を正確にです。4~6は受験的な内容です。
中学受験などで問われるのは、どこまで正確に分類できていますか?
という事です。インプットを繰り返す事と、アウトプット(問題を解く)を
して間違えた所を復習することでできるようになります。暗記部分は、
「AとB」のように対になる場合は、少ない方・例外の方を覚えるのが
基本です。語呂合わせも有効です。
昆虫の基本(中学受験用)
昆虫に共通の特徴
1 体が3つに分かれる:頭、胸、腹
2 足が6本(3対)で胸にある
3 しょっ角が2本
4 2個の複眼(単眼はあるものとないものがある)
5 「気門」(腹の中の「節」にある)とつながった「気管」で呼吸している
(ヒトの場合の「肺」と「鼻の穴」の関係)
昆虫によって違う点
●羽の数:基本は4枚で胸部についている
・4枚:チョウ、バッタ、トンボなど
・2枚:ハエ、アブ、蚊
・0枚:アリ、ノミなど
●完全変態(さなぎがある)と不完全変態(さなぎの時期がない)の昆虫がいる
g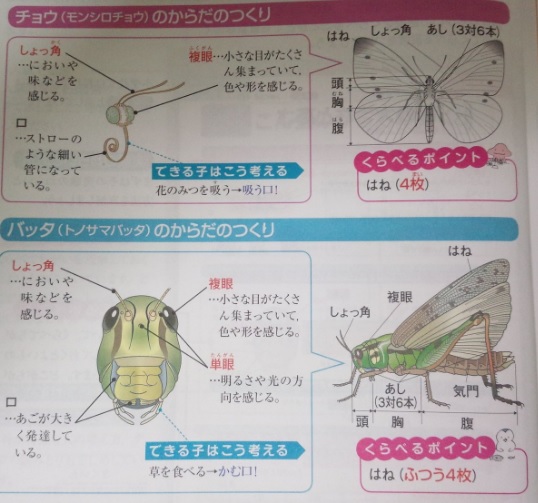
画像出典:『中学入試 くらべてわかるできる子図鑑 理科】 p6
ですので、「足が6本ではない」「体が3つに分かれていない」ものは
昆虫っぽくても『昆虫』ではありません。「クモ」「ダンゴムシ」などですね。
(昆虫ぽいけど違うものは試験上大事ですので、下記で。まずは基本から)
*足が4本のチョウもいるようですが、(試験上は)無視で
昆虫の成長の仕方の違いは「さなぎ(蛹)」の時期があるかないか
昆虫は成長する段階で「さなぎ(蛹)」の時期があるかないかに
分けられます。
さなぎの時期があるものが「完全変態」(ちょう、カブトムシetc)
さなぎの時期がないものが「不完全変態」(バッタ、カマキリetc)
です。
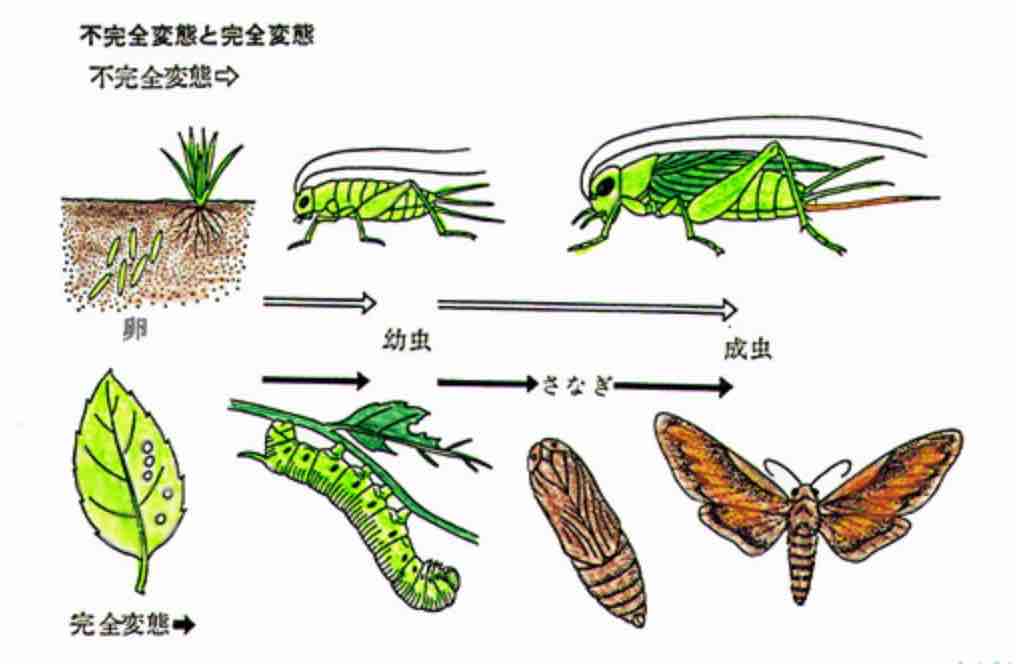
完全変態:卵→幼虫→さなぎ→成虫(ちょう、カブトムシetc)
不完全変態:卵→幼虫→成虫(バッタ、カマキリ、トンボetc)
*「セミ」は「抜け殻」がありますが、あれは幼虫の抜け殻で、さなぎに
はならないので、「不完全変態」です(よく入試に出ます)。
*完全変態の昆虫は、幼虫と成虫の姿が全然違います(不完全変態の昆虫は似ている)。
(セミやトンボは不完全変態ですが、幼虫と成虫があまり似ていませんが・・・)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不完全変態する昆虫の語呂合わせ
か っ と ば せ G(ゴキブリ)!
カマキリ トンボ バッタ セミ ゴキブリ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
数としては、不完全変態昆虫>>完全変態昆虫
なので、「不完全変態昆虫」を覚えてしまった方が良いです。
「かっとばせG!」を知っているだけで結構な問題が解けますよ。
(Gはあまり受検には出ません。みんな嫌いですからね)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
さなぎにならなそう・完全変態ではなさそうな完全変態の昆虫
語呂合わせ 課長(と)飲み母あり
カ、チョウ、ノミ、ハエ、ハチ、アリ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、「完全変態」にある「さなぎ(蛹)」から成虫になるのは、
かなりの見た目のインパクトですよね?例えば、アオムシ→チョウ
実は、アオムシがさなぎになってチョウになるとき、さなぎの中では
幼虫の体がドロドロに分解されるそうです。そのドロドロに分解され
た幼虫の体からチョウの体ができるという仕組みになっています。
さなぎになる前にも、脱皮したりしますが、生命って本当に不思議です
ね~(水野晴郎風。知らんか・・・)。
このあたりまでが「昆虫」の基本です。
以下は応用や中学入試問題を解く上で問われるポイントなどです。
昆虫の分類7種類
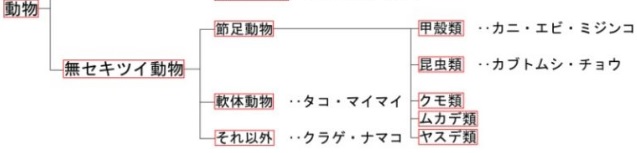
(無セキツイ動物→)節足動物を表にすると以下です。

画像出典:https://yuzupa.com/konchu-map/
昆虫は7つに分類されていますね。ポイントは「カメムシ目」
でしょうか、「セミ」と「アメンボ」が同じ分類です。
昆虫の食べ物・棲む場所(変わるものがポイント)
●幼虫と成虫で、食べるものや棲む場所が変わる昆虫●
が試験では問われる事が多いです。
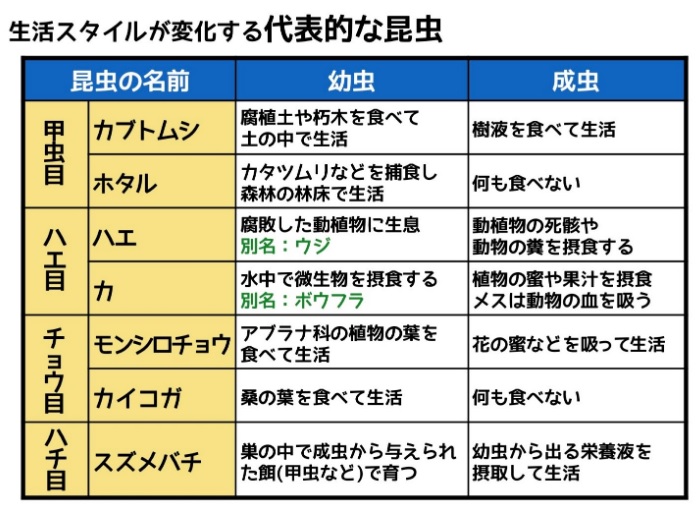
画像出典:https://katekyo.mynavi.jp/juken/9661
幼虫の目的:体を大きくする(あまり動かずに得られるもの)
成虫の目的:繁殖(すぐエネルギーになるもの)
中学入試の理科に出題されやすいのは以下です。
●カブトムシ:幼虫は(土の中の)土や朽木や腐った葉・成虫は(木の上の)樹液
●カ(蚊):幼虫(ボウフラ)は水中の微生物・成虫は蜜や果汁、メスは動物の血
●スズメバチ:幼虫は成虫からエサを与えられる・成虫は幼虫から出る栄養液を摂取
●アゲハチョウ:幼虫は(ミカン科の)葉・成虫は花の蜜
●トンボ:幼虫(ヤゴ)はオタマジャクシや小魚・成虫は生きた虫
●セミ:幼虫は木の根のしる・成虫は木の幹のしる
幼虫と成虫で同じものを食べるのは「テントウムシ(アブラムシを食べる)」「ミツバチ(蜜)」
「カマキリ」「コオロギ」など。さらなる詳細は『中学入試 くらべてわかるできる子図鑑 理科』p14~17を見てください。
昆虫の冬越し
それぞれの昆虫がどのように「冬を越すか」というのは、
中学入試問題の理科でよく問われます。
自然界に生きる昆虫には暖房(コタツやエアコン)ないですからね・・・。
基本的には、冬、昆虫は、暖かい所(巣、土、木の幹etc.)に避難したり、
形態を変化(卵、幼虫、さなぎ)させて生き残ろうとします。
エネルギーを使わないで時が過ぎる(春が来る)のを待つというのが
昆虫の越冬戦略ですね。
【卵・幼虫・さなぎ・成虫】のどれかで冬越しをします。
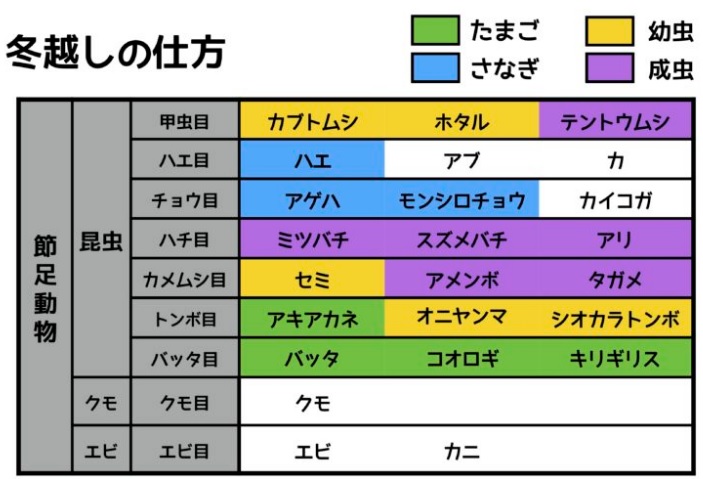
画像出典:https://yuzupa.com/konchu-map/
不完全変態の「カットバセG」(カマキリ、トンボ、バッタ、セミ、ゴキブリ)の
語呂あわせを覚えておけば、それらは「さなぎ」にはならないので、かなり選択肢
が限定できます。
不完全変態の昆虫は「卵」で冬越しする事が多いです(カマキリ、バッタ)。
こちらのYouTube動画に、「昆虫の冬越し」が「ジングルベル」の替え歌で
まとめられています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ジングルベル ジングルベル 冬越しだ~
カマキリ コオロギ バッタは卵
ジングルベル ジングルベル 冬越しだ~
カブ(ト) トンボ ミノガは幼虫だ~
ジングルベル ジングルベル 冬越しだ~
モンシロ アゲハは さなぎだよ~
ジングルベル ジングルベル 冬越しだ~
ハエ(さなぎのものもいる) アリ テントウ 成虫だ。
*この歌を100回くらい歌っていると覚えそうです
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【チョウチョ】は、卵・幼虫・さなぎ・成虫と色々な姿で
冬越しをしますが、「さなぎ」になるのは、アゲハとモンシロチョウ
です。
【ガ】の冬越し:オビカレハは卵、ミノガ(幼虫がミノムシ)・イラガは幼虫、その他はさなぎ
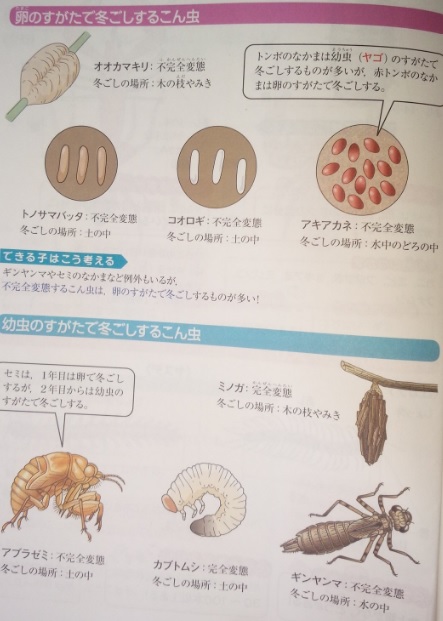
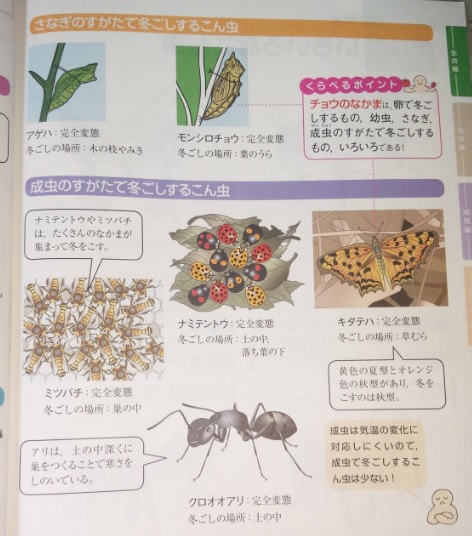
画像出典:『中学入試 くらべてわかるできる子図鑑 理科】 p12-13
まずはどれかだけ(幼虫だけ、成虫だけ等)を覚えて、
あとは、問題をたくさん解いて体で覚えましょう・・・。
昆虫の口と足
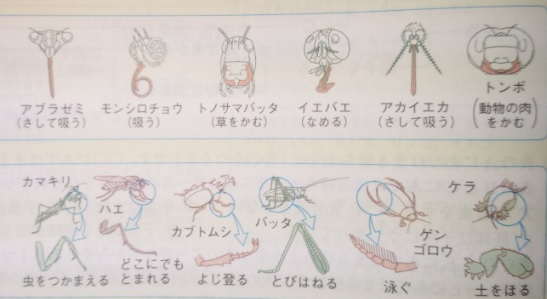
画像出典『塾技100理科』p128
昆虫の「足」や「口」の形はよく試験に出ます。
それぞれ目的合理性(食べ物や行動パターン)にあった形を
しています。何度も見て覚えましょう。
昆虫の卵
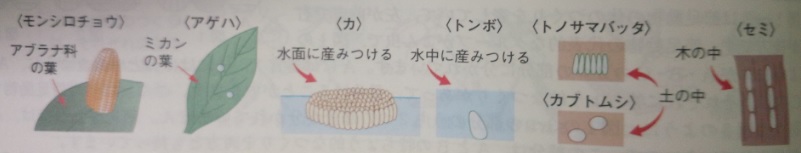
画像出典『塾技100理科』p130
それぞれの昆虫と卵の形をつなげられるようにしましょう。
まとめ―昆虫:体が3つに分かれる・羽の数が違う・完全変態と不完全変態(中学受験用)
昆虫に共通の特徴2つ
1 体が3つに分かれる:頭、胸、腹
2 足が6本(3対)で胸にある
昆虫によって違う点
●羽の数:
・4枚:チョウ、バッタ、トンボなど
・2枚:ハエ、アブ、蚊
・0枚:蟻、ノミなど
・しょっ角が2本
・2個の複眼(単眼はあるものとないものがある)
・「気門」(腹の中の「節」にある)とつながった「気管」で呼吸している
●完全変態(さなぎがある)と不完全変態(さなぎの時期がない)の昆虫がいる
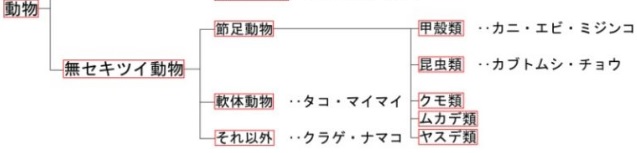
「昆虫」について勉強する場合、以下の順番でやりましょう。
1 「昆虫」の基本(体が3つとか足が6本とか):「昆虫」って何?
2 どんな種類の「昆虫」がいるか(完全変態、不完全変態とか)
3 「昆虫」ではない虫を知る(クモ類、甲殻類のダンゴムシとか)
4 「昆虫」の食べ物・棲む場所(幼虫と成虫で「変わる」のがポイント
5 「昆虫」の「冬越し」(越冬の仕方の違い)
6 色々な昆虫の卵・幼虫・成虫の姿
まずは「1~3」を正確にです。4~6は受験的な内容です。
中学受験などで問われるのは、どこまで正確に分類できていますか?
という事です。インプットを繰り返す事と、アウトプット(問題を解く)を
して間違えた所を復習することでできるようになります。暗記部分は、
「AとB」のように対になる場合は、少ない方・例外の方を覚えるのが
基本です。語呂合わせも有効です。