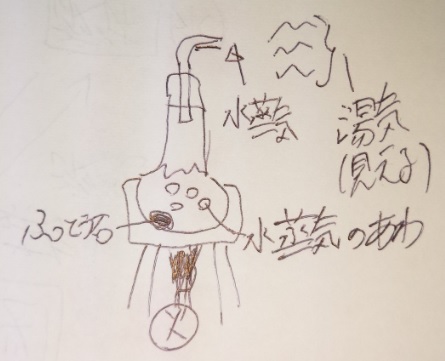
物の熱量・温まり方(熱とは?熱の移動・温度の違う2つの水・カロリー)
『塾技・理科』
この記事では「水の状態変化」について詳細に確認します。
をまだ読んでない方はそちらからどうぞ。
水の状態変化
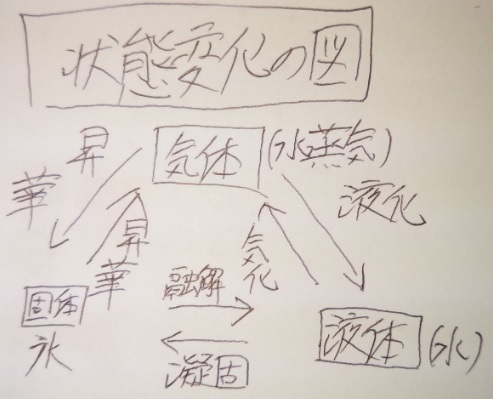
0℃以下の氷を暖めた際の変化
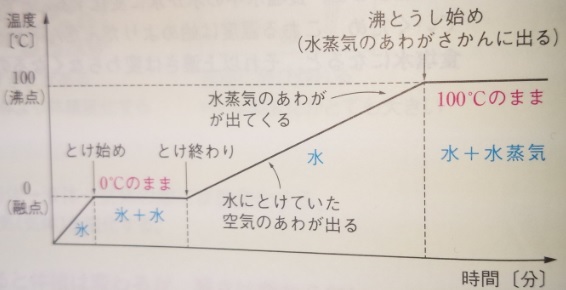
画像出典『塾技100理科』p46
1 0℃まで氷のまま
2 融点(0℃)に達すると氷がとけ始める+温度が上がらなくなる
3 氷がすべてとけると温度が(再度)上がり始める
4 40~50℃あたりで水にとけていた空気の泡が出始める
5 80℃辺りから水蒸気の泡が出てくる
6 沸点の100℃で沸騰し始め、温度が上がらなくなる
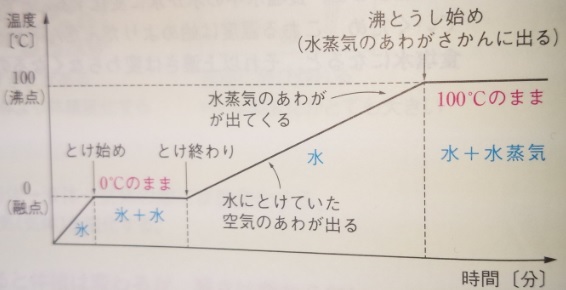
画像出典『塾技100理科』p46
ポイント1:温度が上がらなくなる理由
0℃のとけはじめに温度が上がらない理由は、加えられた熱が、すべて
氷を溶かすために使われるからだそうです。
また、100℃のままそれ以上温度が上がらない理由は、同じように、熱
が水を水蒸気に変えるためだけに使われるからだそうです。
ポイント2:80℃くらいで水蒸気が発生するのはなぜ?
「5 80℃辺りから水蒸気の泡が出てくる」
これは、全体が沸点(100℃)に達していなくても、熱に近いところでは
沸点に達したものが水蒸気になるからです。
ポイント3:湯気(見える)と水蒸気(見えない)の違いは?
「湯気」(見える)、「水蒸気」(見えない)の違いは、湯気は気体の
水蒸気が冷やされた水の粒だから見えますが、水蒸気は気体なので見えな
いままということです。
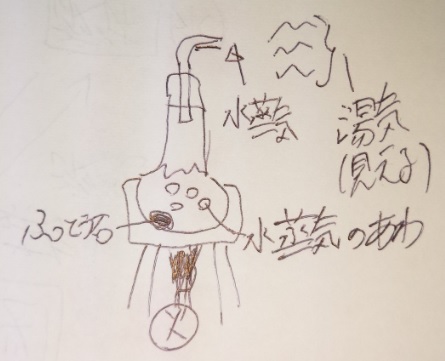
ポイント4:氷はなぜ水に浮くか?
氷(固体)が水(液体)に浮く理由は、同じ体積あたりの重さが
氷の方が軽いからです。
で書きましたが、
水は、4℃の時に体積が最小となり、その前後では膨張します。
(→(同じ体積なら)4℃の時が密度が濃いので水の重さは一番重くなります)
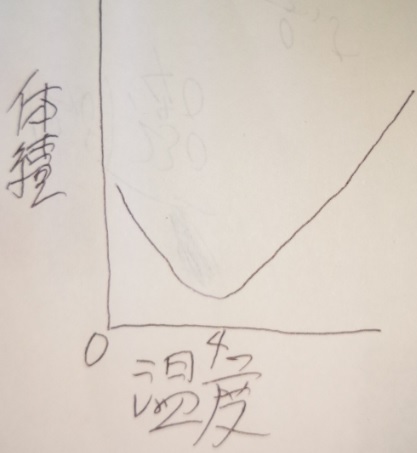
つまり、氷の方が水(4℃が体積最小)よりも体積が増えます。
ただし重さは変わりません。
ですので、同じ体積あたりですと、水の方が氷より重くなり、
その結果、氷は水に浮きます。
ポイント5:気圧の低い所では沸点が低い
1気圧の所では、沸点(水が水蒸気になる)は100℃ですが、気圧の
低い所(標高の高いところ)例えば富士山山頂3776m等では約87℃
で水が沸騰するそうです。
『塾技・理科』
まとめ
以上、
水の状態変化(氷・水・水蒸気)/湯気はなぜ見える?
でした。
【氷を暖めた際の変化】
ポイント1:(一時的に)温度が上がらなくなる理由
→熱が、すべて氷を溶かすため(水蒸気に変えるため)に使われるから
ポイント2:80℃くらいで水蒸気が発生するのはなぜ?
→熱に近いところでは沸点に達したものが水蒸気になるから
ポイント3:湯気(見える)と水蒸気(見えない)の違いは?
→湯気は気体の水蒸気が冷やされた水の粒だから
ポイント4:氷はなぜ水に浮くか?
→同じ体積なら(4℃の)水が重いから
ポイント5:気圧の低い所では沸点が低い
→富士山山頂(3776m)だと約87℃で水は沸騰する。
物の熱量・温まり方(熱とは?熱の移動・温度の違う2つの水・カロリー)
『塾技・理科』