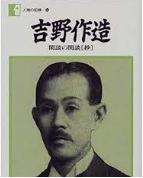
文化史(日本史)の概略・まとめ②(桃山文化・江戸の文化・明治の文化・大正と昭和前期の文化・戦後の文化・現代の文化)
(文化史は、基本的な歴史の流れが分かっていないと意味がないので、
下記の「大正時代」の記事を必ず先に読んでください)
大正時代(1912年~26年)の概略(基本編):大正デモクラシーと第一次世界大戦(1914~1918)
大正文化は「大衆文化」のまとめ
★大正文化は「大衆文化」:庶民が文化の担い手に
・義務教育の普及:1972年(明治5)学制→日露戦争の頃には就学率97%
・女性の社会進出:女性運動(平塚らいてう、市川房枝、「青鞜」)
・マスメディア(新聞、雑誌、ラジオ)の発達
大正~昭和初期(1912~1945)の文化史のキーワードは「大衆文化」9です。
もちろん「大正デモクラシー」(「民本主義」・労働運動、婦人運動)も
大事です。
★吉野作造11(東大教授)の「民本主義」11は総合雑誌9の『中央公論』9に
★美濃部達吉(東大教授、貴族院議員)11の「天皇機関説」11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
★労働運動:友愛会(1912)→大日本労働総同盟友愛会→日本労働総同盟(1921)
★平塚らいてう(雷鳥)『青鞜』。新婦人協会
★部落解放運動→全国水平社(1922年)
「文学」では「耽美派・白樺派」(谷崎潤一郎、武者小路実篤、有島武郎、志賀直哉)と
「新思潮派」(芥川龍之介)。それ以外に社会主義運動の流れをくむ「プロレタリア文学」
も大事です(小林多喜二『蟹工船』)。
昭和に入ると、「新感覚派」(川端康成、横光利一)
★白樺派11:『白樺』8。武者小路実篤、志賀直哉、有島武郎
★耽美派9:永井荷風9、谷崎潤一郎9
★新思潮派5:芥川龍之介11、菊池寛11
★新感覚派8:横光利一8、川端康成9
★プロレタリア文学10:小林多喜二11『蟹工船』、徳永直11『太陽のない街』10
「大正デモクラシー」:吉野作造「民本主義」+美濃部達吉「天皇機関説」
1916年(大正5年):吉野作造「民本主義」
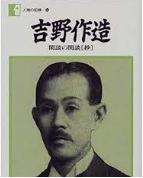
吉野作造11(東大教授)の「民本主義」11は総合雑誌9の『中央公論』9に
発表されました。
内容を簡単にまとめると、
★大日本帝国憲法の天皇主権のもとで国民の意見を尊重する政治を目指す★
となります。ポイントは天皇主権のもとでの民主主義という事です。
ですから、天皇主権を前提に普通選挙→政党内閣を求めます。
天皇機関説(美濃部達吉)
吉野作造の「民本主義」を支えたのが、美濃部達吉(東大教授、貴族院議員)11の「天皇機関説」11です。
「天皇機関説」:天皇主権説ではなく、天皇はあくまで国家の代表・機関。憲法の枠内で機能を果たせ
労働運動:友愛会(1912)→大日本労働総同盟友愛会→日本労働総同盟(1921)
都市化、社会の発展とともに、「労働運動」が起こってくるのも大正時代です。
「メーデー」11が労働者の祝日として1920年5月1日から行われるようになりました。
労働運動:友愛会(1912)→大日本労働総同盟友愛会→日本労働総同盟(1921)
★友愛会11:鈴木文治9が1912年(大正元年)に設立
★日本労働総同盟11:1921年(大正10年)。労働争議10などを資本家相手に行う
1922年(大正11年)には、日本共産党11がソ連共産党の指導下に作られました。
農民関連では、小作争議11が起き、1922年に日本農民組合11(杉山元治郎8賀川豊彦7)が結成された
婦人運動:平塚らいてう(雷鳥)『青鞜』
女性解放運動8が起こるのも(明治末から)大正時代です。
青鞜社11:1911年(明治44年)平塚らいてう(雷鳥)11等が組織した女性解放団体
『青鞜』8:青鞜社が発行した雑誌。「原始、女性は実に太陽であった」
新婦人協会11:1920年(大正9年)。平塚らいてう、市川房枝10等が設立。
明治に『平民』となったはずの被差別部落8だったが、差別は残り、
部落解放運動7が大正時代に起こりました。1922年(大正11年)に
全国水平社11が部落解放団体として設立されました。
「人の世に熱あれ、人間に光あれ」(水平者宣言2)
文学:大正時代→芥川龍之介!
明治の文学と言えば夏目漱石(1867~1916)でしたが、大正~昭和前半でもっとも
大事なのはやはり芥川龍之介(1892~1927)です。
●白樺派・耽美派・新思潮派・新感覚派●
【大正時代~昭和前半の文学】
★白樺派11:『白樺』8。学習院出身者。個性・自我・人道主義7
・武者小路実篤10:白樺派の中心。トルストイ好き。『お目出たき人』『友情』『幸福者』
・志賀直哉11:リアリスト。『暗夜行路』6は近代文学の代表作。『城の崎にて』
・有島武郎(たけお)9:『或る女』5『カインの末裔』3
(・高村光太郎7:詩人+彫刻家。『道程』3『智恵子抄』1)
★耽美派9:官能的、芸術至上主義的。『スバル』
永井荷風9:『あめりか物語』。「三田文学」を主宰。欧米に滞在。『腕くらべ』
谷崎潤一郎9:『刺青(しせい)』3『痴人の愛』4『細雪』4。外国人に人気高い
★新思潮派5:『新思潮』で書いた東大系作家たち。理知的。現実の矛盾。
芥川龍之介11:短編の名手。『羅生門』『鼻』『河童』『或る阿呆の一生』『地獄変』
菊池寛(かん)11:『文藝春秋』2を創刊。『恩讐の彼方に』5『父帰る』1
★新感覚派8:感覚的。文章技法
横光利一8:『日輪』『旅愁』
川端康成9:1968年ノーベル文学賞。『伊豆の踊り子』4『雪国』2
★プロレタリア文学10:労働者や農民を描いた。社会主義・共産主義に賛同
小林多喜二11(1903~33):『蟹工船』10、治安維持法→特高による拷問で死亡
徳永直(すなお)11:『太陽のない街』10
それ以外に、児童文学として、鈴木三重吉8の雑誌『赤い鳥』8や、
大衆文学8として、中里介山9の『大菩薩峠』7や吉川英治7の
『宮本武蔵』2などがある。
1913年(大正2年)創業の岩波書店の岩波文庫3が創刊されたのが
1927年(昭和2年)
★円本9:関東大震災後、1冊1円の本が大ブームに。大正末~昭和初期
★週刊誌7や大衆雑誌8が出てきたのも大正時代。講談社の『キング』10
演劇
演劇の世界では関東大震災(1923年・大正12年)後、築地小劇場11
というのが小山内薫11、土方与志8等によって作られました。
文化住宅11
文化住宅11:大正~昭和初期に流行った洋風住宅。都市サラリーマン向け。ガラス戸+赤瓦。

職業婦人7なども出てきて、モダンガール(モガ)6と呼ばれた。
(モダンボーイ(モボ)もいた)
ラジオ(1925年・大正14年)・映画
ラジオ放送11:1925年・大正4年。治安維持法、男子普通選挙と同じ年
映画10:大正時代は無声映画(サイレント)。活動写真と呼ばれた。
1931年(昭和6年)トーキー8(音と画面が一体)が始まる
甲子園
いわゆる「甲子園大会」(全国高校野球選手権大会)が始まったのは
1915年(大正14年)。当時は、「全国中等学校優勝野球大会」8と
呼ばれた。
(関連記事)
文化史(日本史)の概略・まとめ②(桃山文化・江戸の文化・明治の文化・大正と昭和前期の文化・戦後の文化・現代の文化)
(文化史は、基本的な歴史の流れが分かっていないと意味がないので、
下記の「大正時代」の記事を必ず先に読んでください)
大正時代(1912年~26年)の概略(基本編):大正デモクラシーと第一次世界大戦(1914~1918)

